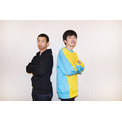
お笑い芸人や俳優、モデル、アーティスト、経営者、クリエーターなど「おもしろい人=タレント」の才能を拡張させる“タレントエンパワーメントパートナー“FIREBUGの代表取締役プロデューサーの佐藤詳悟による連載『エンタメトップランナーの楽屋』。
第五回は『週刊少年マガジン』(講談社刊)の編集長を務める川窪慎太郎をゲストに迎える。
元お笑い芸人のマネージャーという経歴を持つ佐藤氏と、編集者として漫画家に向き合う川窪氏。クリエイターとの付き合い方から、漫画ビジネスの現在について話を聞いた。
参考:アニメ『チェンソーマン』異例となる「100%出資」の理由は? FIREBUG佐藤詳悟×MAPPA大塚学が語り合う“アニメビジネスの未来”
■「1982年会」のメンバー同士が取り組んだボイスドラマ
ーーまずは川窪さんと佐藤さんの最初の出会いや関係性についてお聞きしたいと思います。
川窪:いまは「1982年会」という同い年の集まりの一人として佐藤くんとほか何名かで定期的にお会いしています。その会に参加するきっかけになったのは、当時SEKAI NO OWARIのマネージャーを務めていた宍戸(亮太)くんと元々繋がっていて、誘われたのが最初でした。そこで初めて佐藤さんとお会いしたんです。
佐藤:一番多かったときは30~40人くらい集まっていたよね。いまは1年に1回くらいのペースで開催しているけど。当時は現場を担当しているメンバーが多かったから、仕事に繋がるということはあまりなかったかな。でも最近は昇進してみんな偉くなっているというか。仕事の話もできるようになって、ようやくそんな時代が来たなと思っています(笑)。
川窪:佐藤さんとも最近、一緒に仕事もするようになりましたが、仕事関係なく僕が困ったときに「こういう人っていませんか?」と佐藤さんに声かけると「いるよー!」と返事が返ってくる、というやりとりが多いかもしれません。占い師とかサウナを作れる人とか。本当になにか言えば出てくる“ドラえもん”のような存在として、頼りにしているんですよ。
佐藤:仕事の絡みとしては偶然もあるんですけど、いきものがかりの吉岡聖恵の楽曲で講談社さんの作品とタイアップさせてもらったりしていました。
川窪:明確にひとつ仕事をしたなと感じているのは、一緒に原作から漫画を作ったことですかね。
佐藤:そうそう、ちょうどコロナ禍で何もすることがなくなったとき、川窪くんに相談したところ、「ボイスドラマをたくさん作りたい」という話になって。ちょうどアミューズさんもメディアを立ち上げるタイミングだったので、3社でボイスドラマを立ち上げてからコミック化して展開しよう、という形で進んでいきました。
川窪:基本的にうちは著作権者が漫画家や小説家だったりするわけで、その運用をさせていただくビジネスになっているんですが、会社としても「自分たちも著作権を持つ」というチャレンジをしようと思っていて。こうした背景もあり、ボイスドラマを原作として、それをコミカライズしたり映画化したりできたらいいねと話していました。
佐藤:ボイスドラマからLINE漫画、コミックの順番に展開していきましたよね。
川窪:はい、そうですね。
ーー以前、MAPPAの社長の大塚さんを取材した際に、「現在のアニメビジネス」の全体の整理もさせていただいたんです。その中で「アニメ業界は周りのビジネスに引っ張られていて、アニメ制作会社の立ち位置が少しずつ変わっている」という話も出たんですが、いち読者として「現在の漫画ビジネス」を考えてみると、結構盛り上がっている印象を持っていて。そのあたり、川窪さんはどのように感じていますか?
川窪:去年(2022年)までが好景気だったんじゃないですかね。好記録を2021年、2022年と2年連続で記録したので。
ーーということは多くの人に読まれたという認識で合ってますか。
川窪:おっしゃる通りで、単行本の発行部数も好調でした。やはりコロナ禍で外に出ない状況が続き、家でできることに漫画を読むことも入っていて、その影響が大きいと感じています。いわゆる巣篭もり需要が明確にあったわけですね。それが去年の下半期あたりかな、コロナ禍が落ち着きを見せた大型連休を境に下がってきています。
佐藤:コロナ禍の影響はもとより、電子書籍が伸びたとかはあります?
川窪:それもありましたね。コロナ前から紙が落ちているぶんを電子書籍が補って、少しプラスに転じるというのが3~4年ありました。
佐藤:そこにコロナ禍が来て爆発したというわけか。
川窪:はい、外に出て買いに行かなくても電子書籍で漫画が読めるため、人気が高まったという感じです。
■火のつき方が「読んだら面白い」から「読む前から面白い」へと変化している
佐藤:コンテンツの要素の部分はどうでしょう。クリエイターがデジタルになったことで、修正がしやすくなったとか、入稿期限ぎりぎりまで面白いコンテンツを考えられるようになったとか。
川窪:うーん、作品として読者に刺さるようになったかは明確にわかりませんが、やっぱり世の中にクリエイターが増えたのはすごく感じています。それは漫画だけではなく、イラストや歌、映像など、クリエイトするための敷居が下がっていると思うんです。クリエイターの数が増えたことで、結果的に作品数も増加しているのも好景気になったひとつの要因に挙げられるかもしれません。
佐藤:作品の出し先はどのようになっているの?
川窪:週刊少年マガジン編集部は、雑誌の『週刊少年マガジン』と『別冊少年マガジン』、アプリの「マガポケ(マガジンポケット)」の3つを運営しています。昔と比べても、アプリのおかげでクリエイターの出し先が増えていますね。紙とアプリの一番の違いは収容量で、アプリの方は言ってしまえばどこまでも載せられるというか。もちろん、担当できる漫画編集者の人員や利益分を鑑みて一定の限度はあれど、紙よりもだいぶ上限はない感じです。
佐藤:作品の伝わり方、流行り方に関しては、川窪くんが講談社に入った17年前と比べて、火のつき方は変わりました?
川窪:どうだろう。おそらく変わったんじゃないかな。やはり昔は書店に置いてあることがすべてでしたから。面白い順に我々が漫画を刷っていて、刷られた量に応じて書店のスペースが取られていくと、来店した人の目に入りやすくなるので、手に取るようになるわけです。書店に行くことで面白い漫画や小説の情報を得られる時代だったんですね。
でも、いまはSNSですぐに流行っているものをキャッチできるので、言い方が正しいかはわかりませんが「SNS映え」するものが持てはやされている感はあります。例えば「グロい」、「怖い」「驚きがある」というようなひと言で言いやすい企画ものとかはSNSで取り上げやすく、流行る傾向があるなと思っています。
佐藤:形容詞で言うと、年ごとに流行るものがあるんですかね。
川窪:いまは「エグい」が強いですね。もしかしたら、僕の担当作でもある『進撃の巨人』もその一因になっているかもしれません。いまのトレンドとして、人が死ぬ漫画や主人公が辛い目に遭うような過激描写が多くなっているのもあり、エグいという言葉が持てはやされています。
佐藤:違う形容詞が生まれると、みんなそれにつられてトレンドが変化してくるようになるですか?
川窪:それで言うと一気に変わるのではなく、ゆっくりとトレンドが移行してくるとは思います。でも結局はSNSでの発信のしやすさがあるかどうかが根底にあるわけで。「読んだら面白い」のではなく「読む前から面白い」と表現した方がわかりやすいかもしれません。「読む前から面白い」というのは、SNSで紹介された時点で興味を惹かれるほど面白く感じるという意味です。
ーーSNS広告で漫画を知ることが多いと思うんですけど、『食糧人類 ーStarving Anonymousー』はまさにそれだなと感じました。
川窪:そうですね。あとはうちの作品で言うと、『十字架のろくにん』という漫画があって。親を殺されてしまった主人公が、親を殺した同級生に対して何年もかけて復讐していくという物語になっているんですが、当初これは『別冊少年マガジン』で始まった作品でした。
その後、単行本として出したんですが、売れ行きが伸びずに途中で打ち切りになったんですよ。実は僕が打ち切りの判断をしたんですが、作品も読んでいて面白いと思っていたし、作家の才能にも可能性を感じていたものの、部数が伸びなかったこともあり、「紙では継続できないけどマガポケに移籍してもう少しチャレンジしよう」と部内で話し合ったんです。そしたら、そこからめちゃめちゃ売れて。看板作品になるくらいバズったんですよ。
佐藤:紙とアプリでは何が違ったんですかね。
川窪:マガポケの読者層が紙と異なること、あとはアプリなのでバナー広告を出すときにマガポケの宣伝として『十字架のろくにん』を使い、広告運用したところ、かなり反響がありました。
内容としても過激というか、わかりやすいじゃないですか。僕らからすると、最初から面白いと思っていたんですが、ただ書店に置いているだけではなく、わかりやすいバナーを作成することで、その魅力に気づく人もいるわけで。SNSが普及しているからこそ、「わかりやすさ」や「エグい」といったものがキーワードになり、それが多くの読者に刺さるきっかけになるとあらためて実感した事例でしたね。
佐藤:バナー広告のクリエイティブで気をつけていることってあります?
川窪:僕が直接関わっているわけではなく、別の者が担当していますが、瞬間的にわかりやすく、ぱっと見で興味をそそられるようなクリエイティブを意識していると思います。また、書店や漫画アプリ自体が出すバナー広告もあって、それはもっと顕著で。
バナー広告に載るキャッチコピーって、漫画では一部分ともいえる要素を漫画全体を示すかのように上手に表現したりしていて。そういう見せ方の工夫も相まって、グロさを読者にピンポイントに伝えていくバナーの作り方になっていますね。もちろんエグさやグロさがすべてではないですけど。
■漫画家あっての商売だからこそクリエイターの数が求められる
佐藤:面白いと思っていても、売れなかったり。あるいはひょんなことがきっかけで急に売れたりと、ヒット作を生み出すのって難しいですよね。運も左右されるかもしれないし。
川窪:そこは難しいポイントで、「作りたいもの」と「売れるもの」が2つあると思っていて。これらは作家にも編集者の中にもあるわけです。編集者も実績を出したいがために、サスペンスやホラーといったグロいものが流行れば、みんなそっちに寄っていく。
そうじゃないものも作ろうと現場は思うかもしれないけど、それだと売れないし。やりたいものが、チャレンジしたいものができないという葛藤も生まれる中、やはり流行りのジャンルにどうしても偏るという状況は拭えないかもしれません。
佐藤:ビッグヒットというのは、流行りのシーンに合わせるからこそ、生まれるものなんですか?
川窪:どうでしょう。『進撃の巨人』を作家とやろうと話していたときも、別に「何か新しいものを作ろう」とか「今の漫画古いよね」とか「常識に囚われないようにしようぜ」とか、あるいは「流行に乗ろう」などは、全く意識していませんでした。単純に作家の中にあったものをやろうというスタンスでしたね。自分の作品に対して「魂を込めて作ってほしい」と思っているんです。そうじゃないと、つまらないじゃないですか。結果として諫山さんの中に「他人の心を揺さぶる何か」があったということなのかなと理解しています。
編集長になったいまでも、こうした気持ちをすごく大事にしていますね。正直、売れる売れないはわからないので、「一緒に面白いものを作ろう」という気概を持って取り組んでいるつもりです。
佐藤:編集長になってからは、これまでのように漫画家さんと接するよりも、部内の編集者とやりとりすることが多くなっていますか?
川窪:基本的には部長としての振る舞いがメインになっていて、クリエイティブよりも人の管理の方が多いですね。部員とのコミュニケーションなど、思っていた以上に管理職だなと感じています。一方、週刊少年マガジンに載る漫画の連載案は、僕ひとりで読み、僕ひとりで決めていて。連載の継続有無も自分に決定権があるので、一部だけですがクリエイティブにも関わっています。
ーー細かい中身に関しては、各編集者に任せている感じでしょうか。
川窪:実は僕含めて歴代の編集長はみんな、連載中のものに口を出すことはないんですよ。もちろん、「最近、面白いね」と感想は伝えることはあるけど、「いまの方針は間違っているから変えていきなさい」とかは言わないかな。部員の裁量が大きいのはずっと変わらず、そういった社内カルチャーが自然と根付いているのではと思っています。
佐藤:マインドのところを言ってあげるのが多いということかな。
川窪:そうですね。あとはシステムですかね。「漫画家あっての商売」なので、漫画家を集めるにはどうすればいいかを考えています。
佐藤:漫画家の数が増えれば増えるだけ、ヒットが生まれやすいと。
川窪:最近はつくづくそう思っていますね。どんなに優秀な編集者がいたところで、漫画家が0人だったら、何もできないわけで。それを起点に考えると、優秀な漫画家の数が多いに越したことはないわけです。
佐藤:漫画家からの応募は、どういう経路が多いですか?
川窪:コロナ前は電話して編集者とアポを取る持ち込みが多かったんです。それがコロナ禍で、物理的に持ち込むのが難しくなったので、以前よりも持ち込みは減っています。現在は賞に投稿する、通常の持ち込み、フォームから応募するWEB持ち込みの3つが同じくらいのボリュームになっていますね。
漫画家の数で言えば、7~8年前から減り始めていたのが、近年になって再び増え始めていると感じていて。デジタルの発達で漫画を簡単に描けるようになったり、持ち込み以外の経路も増えたりしています。
ーー編集部が扱っているものの中には、SNSで作品を公開している漫画家に逆オファーするのも増えているんでしょうか?
川窪:そのパターンも最近多いです。イラスト描いている人に「漫画描いてみませんか」とDMを送ることや、他誌に持ち込みしていた人に対して「うちでやりませんか」とメッセージするなどしています。
ーーつまり、SNSの普及によって、昔よりも漫画家と接する機会が多くなったということですか?
川窪:そうですね。昔は積極的に漫画家を開拓しにいくためには、出張編集部やコミケで名刺を渡すくらいしか手段がありませんでした。そんななか、優秀な漫画家の“引き抜き合戦”も横行しているため、昔のような出版社へのロイヤリティ(忠誠心)は薄れてきていると思っています。
それこそ、一度マガジンで始めたらずっと継続するようなものだったのが、現在は新しい環境に移ろうと思えば、作品を持っていろんな出版社を渡り歩けるわけで。
ーーそうなると、他社の編集者と取り合いになっているような状況なんでしょうか?
川窪:競争状態になっていると思いますよ。昔は連絡先を知ろうと思えば、描いている出版社に直接聞かないとわからなかった。それがブログのメールアドレスが記載されているとか、Twitterやっているとかで、だいぶ漫画家と連絡が取りやすくなりましたね。
ーー以前は編集者は、縁の下の力持ちといったあまり表に出ない存在だったのが、SNSによってそういったイメージも変わってきている気がします。
川窪:自分の名前を知ってもらうために、毎日のようにコンテンツを考えて投稿している編集者もいますね。これからの時代、それが必須かと言えばそうではないかもしれませんが、マガジンやジャンプクラスの規模があれば、ありがたいことに先ほどの持ち込みがちょこちょこあるので、なんとかやっているわけですよ。
それが、もっと規模が小さくなっていくと、持ち込みが望めないので、SNSを頑張って漫画家に声をかけていくのが求められると思います。
佐藤:吉本興業でも、当時は毎年1000人以上が養成所に入っていました。他の芸人の会社よりも圧倒的に若い人がたくさん入ってくるから、確率でいうとそれだけスターも生まれやすい。いかに才能あるクリエイティブな人が集まれるかが肝になるんじゃないかと。
川窪:受け皿になれるかが重要ってことですよね。
■縦読み漫画の隆盛で既存の読者やクリエイターが離れている?
佐藤:あと気になっているが、たまに海外の人と仕事の打ち合わせをする際に、「Netflixで何を観ているんですか?」と尋ねると、日本のアニメと答えるケースが多いこと。いわばオタクじゃない海外の一般の人に、日本のアニメが観られているのは、単純にすごいなと思っていて。アニメの大半は漫画原作が多くて、それが漫画業界にとっては目に見えるくらいプラスになっているんですか。
川窪:10年前は「いつか紙と電子の売り上げが逆転する時代が来るかも?」と言われていたのが、今は「そのうち国内と海外の売り上げが逆転するかも」と言われています。
佐藤:デジタルになっている影響が大きい?
川窪:それで言うと、ちょっと違うかもしれません。講談社は北米にKUPという子会社を持っており、そこの人とたまに話すと「アメリカ人は紙しか読まない」って言うんですよ。
佐藤:へー。そうなんだ。アメリカ人はみんなスマホやタブレットで電子書籍を読んでいるかと思った。
ーー海外の展開でいうと、『進撃の巨人』が最終回を迎える1年半くらい前、国内で毎号発売されるたびにSNSで話題になっていた印象です。逆にそれが海外でもリアルタイムで楽しめるような状況だったんでしょうか?
川窪:当時で言うと、いくつかの作品は同時配信していて。『進撃の巨人』も日本で雑誌が発売される同じタイミングで、海外でも配信をしていました。
ーーやっぱりそういう動きは、ファンの熱量からしても必須になってきているんでしょうか。
川窪:はい、必須だと考えています。海外のイベントを通して、日本の作家へオファーもたくさん来ますし、需要はあると感じています。作家を海外に連れて行ったところ、有名な映画スターやミュージシャンが来たくらいの歓迎ぶりだったみたいで。日本のコミックアーティストがこんなにもリスペクトされているというのを、あらためて感じることができたと聞いていましたね。
佐藤:自分だと、「Netflixで面白いと思ったアニメは漫画の原作を買う」という流れがあるんですが、これは海外の人だとどういう状況なんでしょう。
川窪:海外はアニメの方が圧倒的に入りやすく、最初の入りが漫画というのはあまりないかもですね。
佐藤:韓国発の縦型漫画はライバルとして認識していますか。
川窪:うーん。ライバルになっているのかな。海外の人は「漫画といえば横だよね」という感覚がなく、WEBTOONで漫画を縦読みするのが普通だと思っていて、すんなり入っていけるんです。一方で講談社としては、まだ本格的に縦読み漫画には参入しないんじゃないかと思います。
ーーライバルとしての実感は、まだそこまでないわけですかね。
川窪:ピッコマがすごい勢いで支持され、売上が伸びているわけですが、既存の漫画が食われているとか、漫画の読者が減っているとか、あるいはクリエイターが取られているとかは特に感じていないですね。
佐藤:日本は年間に出している漫画原作の数って、海外のそれと比べると異常なくらい多いですよね。ちなみに、どのくらい新しいものが生まれているんですか。
川窪:うちの編集部でいうと、年間で目標にしているのが35本くらいですかね。トータルで連載しているのはその2倍強です。
佐藤:半分くらい入れ替わるんですね。これは自然とこの割合になっている?
川窪:あらためて数字にしてみると、こんなに入れ替わっているんだと感じますが、全然無理はしてなくて。円満終了するものと、残念ながら打ち切りになるものを、普通に数字を見てやっていくと自然とこういう割合になっていくわけですね。ただ、油断すると新規の連載が減ってしまうので、そこは意図的に新しいものを増やす意識は常に持っています。
ーー連載終了について、数字を定点観測していくなかで、これまでは発行部数やアンケートが中心だったのが、SNSの反響も重要になっていると思っていて。SNSはどのくらい判断材料として重要視していますか?
川窪:どうなんですかね。僕個人はそこまでSNSは重要視していないかな。やはり、アンケートと売上を一番見ていると思います。ちなみに、アンケートで一番気にしているのは「人気はあるのに購入されていない」というパターンなんですよ。
佐藤:面白いのに売れていない、というのが可視化されるとなると、突き詰めていけば「もっと面白いものを作るしかない」というのに行き着くわけだ。
川窪:まさにそうですね。
■SNSが全盛になっても「サプライズヒット」は生まれる
佐藤:川窪くんに伺いたいことがあって。テレビがベースだった昔は、聞いている音楽も100人中90人くらいが同じだったわけだけど、今って音楽も漫画と同様に、売れるシーンがいくつかあるんですよ。ただ、最近の紅白を見ていても、みんなが口ずさめるような曲は生まれていなくて。漫画の場合だと、SNSによって趣味嗜好が多様化されてきているんですか。
川窪:好みが細分化されているなとは思っていますね。自分が17年前に編集者になった頃にはなかったジャンルも結構出てきていますし。例えば料理ものに関しても、昔は料理人として頂点を目指したり、美食を極めるみたいなものくらいしかなかった。それが今ではキャンプしながら食べたり、ゲテモノ料理を食べたり、おっさんが1人で食べたりと、ジャンルが細分化されている。恋愛に関しても、男女の色恋だけじゃない、ジェンダーレスのものが出てきたり。そういう意味では、マイナー紙からも人気作品が生まれてくるようになってきていますね。
佐藤:漫画はどのくらいのファンベースを持っていれば、成り立つものなんですか。
川窪:5万人いれば十分、10万人いれば人気のヒット作という感じですかね。ジャンプアップの基準だと、10万人を超えていけばその先の50万、100万人を目指せるポテンシャルがあると思います。自力で10万人のファンがいれば、それを他力で増やしていくみたいな。
佐藤:これは音楽でも芸人でもそうだけど、やっぱりある程度のファンベースがないと、そこから先にジャンプアップできないというのは感じています。結局、飛躍するためには面白いものを作る、良い曲を出すとかに帰結するんだなと思いますね。
川窪:部員に言っているのは、「アンケートで1つでも上の順位を狙おう」ということです。10位なら9位を、5位なら4位を目指そう、という風に言っていますね。
あとはアニメや映像がなくても、「自力で10万部を目指そう」とも伝えています。その先は運や時流に左右される部分なので、読めないところでもありますが、10万部までは作家と編集が一丸となって頑張れば不可能じゃない。こうした思いを胸に、日々取り組んでいるような状況です。
ーー人気の可視化という面では、SNSの反響によって、だいぶわかりやすくなっていると思うのですが、そういう意味だと、予想外のサプライズヒットはあまり生まれなくなっているといった状況もあるのでしょうか?
川窪:いや、サプライズもまだまだある気もしますね。ちょっと質問の意図と外れるかもしれませんが、例えば『鬼滅の刃』や『東京リベンジャーズ』も雑誌内では大人気でしたが、その人気に見合う売上には至っていなかった。そんななかでアニメ化されたことで、一気にブレイクし、ウルトラヒットにつながったわけです。それをサプライズと呼ぶかはわかりませんが。
佐藤:もともと熟成されていたものがあったからこそ、アニメで爆発したんだろうね。
川窪:面白さは何も変わっていないのに、アニメになると急にバズるのは、未だに不思議というか。また、アニメだと1話目2話目だけでも爆発的に売れるわけなんですよ。これって、漫画だと50話いっていても売れないのに比べて、すごい差だと思っていて。アニメだと1話、2話くらいで火がついてるのに、なんで漫画だとそうならなかったのか。もちろん、アニメの素晴らしさはあれど、単にアニメになったら面白くなるわけでもなく、やっていることは変わらないので、自分でもヒットの要因が掴めていないんですよね。
佐藤:音楽のアーティストでもファンの属性によって、流行っている感じがする人と、身内の感じになっている人がいますよね。K-POPは外を向いているので、すごくトレンディーで拡散されている印象を受けます。
ーー2人の話を聞いて思ったのが、漫画とアニメで「口コミの伝導率」が違うということでした。アニメは「これ面白いよ」と伝えたときに割と見てくれる一方、漫画だと買って読むまでのハードルがある。「アニメが始まってからでいいや」と考える人も多いのかもしれません。
川窪:後はアニメの方が面白さを伝えやすいですよね。PVの映像も気軽に見れるし、ストーリーが気になったら、まずは自分が使っている動画サービスからで気軽に1話から視聴できる。
また、漫画を電子で買う人と紙で買う人では層が分かれていて。紙で買う人の方が年齢層が若いんですよ。わかりやすく言うと、クレジットカードがなかったり、スマホ決済が許されてないなど決済能力のない人が、必然的に紙を買うというわけなんです。
■2人で異なるクリエイターとの距離感や仕事への向き合い方
ーーお二人はプロデューサーと編集者という、クリエイターと近い立ち位置でものづくりに携われる職種ですが、そのなかで「クリエイターとの適切な距離感」や「自分の中で大事にしていること」についてお聞きしたいです。
川窪:自分の中で決めているのは「あまり深入りしない」ということです。僕はサラリーマンゆえ、生涯マネージャーでもオーナーでもない。いつ担当から外れるかもわからない。どこまでいっても、仕事としてやっているだけなので、深入りしすぎないようには心がけていますね。「人生を背負うなんておこがましくて言えない」というスタンスでお付き合いしていくのを、マイルールとして定めています。
佐藤:距離感は人それぞれの考え方はあると思います。でも僕なら、せっかく関わっているなら、何かしてあげたいなという気持ちはありますね。この人にとって、「自分ができることは何か」というのは常に考えています。人によっては運転もしたし、売上を上げたいと思っている人にはサポートして利益を出したり、露出を増やしたいと考えている人には、その機会を提供したり。
基本的には「こうしたい」というのを聞いて、自分ができることをしてあげていた感覚が強く、冒頭の方で川窪くんが僕のことを“ドラえもん”と呼んでいたけど、そのような存在でありたいなと思っています。
もし僕がホテルのコンシェルジュをやったら、かなりワークするんじゃないかと(笑)。そう感じるくらい、いろんな人の要望をヒアリングして、それに応えたいという気持ちが誰よりも強い。「佐藤でマネージャーでよかったわ」と言われるのが最高の褒め言葉というか。人によって求められるものが異なるわけで、それに応えようと必死にやっていたら、比較的なんでもできるようになった感じです。
川窪:そうすると「異を唱える」ことはあまりしないということ?
佐藤:例を挙げると「年収を倍にしたい」と言われたときに「これやったらいいんじゃない」とアドバイスするわけです。でも、「それはやりたくない」という返事だった場合は「でも、年収を倍にしたいんじゃないの」という切り返しはしますね。ゴールに対してやらなくてならないことは、提案していました。
幸いにも吉本のマネージャーだった頃は、ある程度の関門というか修羅場を通ってきた芸人さんを担当させていただいていたので、そういう意味ではその人の願望と行動が乖離しているということに、出くわすことはあまりなかったです。
ーー川窪さんは逆に一線を引くようなスタンスを貫いているんですか?
川窪:一線を引く代わりに「都合の良い嘘はつかない」というのは大事にしています。僕はサラリーマンとして、自分の利益を追求するし、ビジネスにおいてはたくさんの大事な人がいるので、そういう立ち位置を明確にした上で作家と向き合っていますね。
ーー最後に今後お二人がやっていきたいことがあれば教えてください。
川窪:今まさに佐藤さんと話しているものがあります。
佐藤:はい、現在進行中のものとして、他の会社で作ってもらっているサービスがあるんですけど、それを一緒にマガジン編集部とやりたいと思っていて、ちょうど話しているところです。会社を経営し始めてから7年くらい経つんですけど、本当にいろんなことがありました。そのなかで感じたのは、エンタメ業界におけるチームビルディングやマネジメントのことについて学べる機会があまりないこと。そういったエンタメ業界あるあるの悩みごとを相談でき、ナレッジをシェアできるような場を作りたいなと考えています。
(取材=安田周平・構成=古田島大介)



コメント