
宇宙飛行士の野口聡一さんはJAXAを57歳で退職。現在は、民間企業の最高技術責任者として気候変動問題に取り組むなど、多岐にわたって活躍しています。順風満帆に見える野口さんですが、2回目のフライトを終えた2009年当時、ロシアの宇宙船ソユーズに乗った日本人として初の長期滞在(約5ヵ月半)の偉業を成し遂げた後、燃え尽き感に襲われることとなります。その後は日本で管理職として働きながら、転職した同僚や先輩を尋ねたり、ライフプランを改めて考えたりする時間を過ごしました。本記事では、野口さんの著書『宇宙飛行士・野口聡一の着陸哲学に学ぶ 50歳からはじめる定年前退職』(主婦の友社)から一部抜粋・再編集し、野口さんがセカンド・キャリアに進む決意をするまでに影響を与えたことを紹介します。
人生を変えた毛利衛さんの言葉
2度目のフライト後に訪れた行き詰まりの後、貴重なアドバイスをもらうようになった先輩たちの中に、キーパーソンと呼べる方がいます。
尊敬する宇宙飛行士、毛利衛さんです。スペースシャトルに搭乗した初めての日本人宇宙飛行士。私にとって、最初はテレビの中の人でした。私が宇宙飛行士に選ばれたときには試験官であり、直属の上司だった時期もあります。圧倒的な存在感と威厳を感じさせる方でした。
付き合い方が変わったのは、1996年にNASAへ派遣され、宇宙飛行士訓練コースの同期生になったとき。毛利さんは2回目のフライトを控えていて、当時48歳。私は31歳で、こわいもの知らずでした。
「毛利さん、もう一度頑張りましょ」みたいな感じで接し、一緒に体力訓練をした仲。尊敬すべき先輩でありながらも同期生という、非常にまれな関係にありました。同期生とはいっても、やはり毛利さんは常に私の1周先、2周先を行っている人なので、いろんなタイミングで相談をしていました。
そして、転職を考える上でも、貴重な存在でした。毛利さんは2度目の宇宙飛行を終えた後、1年も経たないうちにJAXAから転身し、日本科学未来館の館長に就任しました。
「野口君、宇宙だけ見ていると、世間が狭くなるよ」が毛利さんの口癖でした。宇宙事業を相手にしているだけでは、物の見方が狭くなってしまうというのです。実際、毛利さんは深海調査船に乗ったり、南極に行ったりと活動の幅をどんどん広げていきました。
民間の世界へ
私が毛利さんに転職の相談をしたのは、3度目のフライトに入る直前でした。
「このフライトが終わったら、次、どうしようかと考えているんです」
「だったら、野口君は社長になる方がいいよ」
毛利さんは私に、JAXAという肩書きで仕事をするような官僚的な社会の中にいるよりも、民間の世界に向いていると言いたかったのです。社長と言ったのは誇張でしょうが、自分のやりたいことを外に求め、そこでリーダーシップを発揮する方がいい、だからJAXAにこだわる必要はない、と。いや、毛利さんはもっとはっきりと言いました。
のちに「JAXA退職」を決意させた毛利氏の一言
「宇宙にすら、こだわる必要はないんだよ」
宇宙も楽しいけど、ほかにも楽しいことがある。宇宙よりも大事なことはいっぱい世の中にあるんだ、と教えてくれたのです。毛利さんのアドバイスは、時を経て私のJAXA退職にも直接つながっています。
「場の支配力」がなくなったコロナ時代
私が3度目のフライトを終え地球に帰ってきたのは、新型コロナウイルス感染症が世界中で蔓延していた真っ最中の2021年のことでした。
オフィスに行っても、出社している人はほとんどいない。オンライン会議などが急激に多くなり、結局、在宅が多くなって、就業時間中は業務をしているとはいえ「職場」に縛られる時間が大幅に減りました。それは間違いなく、転職を含め自分のライフプラン、キャリアチョイスを考えるきっかけを与えてくれたと思います。
そもそも日本社会は、所属する組織の「場の支配力」があまりに強すぎる。全構成員が常に100%業務に没頭することを求められます。職場に居ると日々の業務や些細な問題に忙殺されて一日があっという間に過ぎ去っていく。
そんな状況では転職はおろか、自分自身のライフプランを考える心の余裕さえ持てないのが実情でしょう。
この点、私はコロナ体制下で、場の支配力が一時的に弱まった恩恵を受けたとも言えるのです。コロナ禍の時代、会社の持つ「場の支配力」からいったん解放されたことは、私だけに限らず、日本社会にとっても画期的なことだったと思います。
どこでも仕事ができるという新たな労働環境が創出され、新たな時代の到来を予感させました。だいたい、自宅から遠い勤務地までの長い道のりをずっと電車に揺られて行く「痛勤」がなくなり、まるで違った日々の景色が見えたものでした。
新型コロナウイルス感染症が蔓延した2020~2022年ごろは、確かに一つの実験的な時期でした。「三密回避」が求められ、個と個を切り離し、接点を極力減らすために会社には行かないことになり、この一時期だけは、どこでも仕事ができるようになりました。
日本はあっという間にコロナ禍前へ逆戻り
個と個を切り離して集団で働かなくなったとき、果たしてこの社会は回っていくのか。日本らしい「場の支配力」が働かなくなると社会は機能しなくなるのか、それとも新たな体制みたいなものに変化していくのか。その辺り、社会のあり方をめぐる壮絶なせめぎ合いがあったと思います。
ところが、日本社会は変化を嫌いました。新型コロナ問題が沈静化し徐々に平常状態に戻る過程で、日本社会には「場の支配力」が復活してしまったように思います。
アメリカやヨーロッパでは、一度リモートの楽さを知ると、人々は容易には元の集団化した社会へと戻らなかった。日本はあっという間にコロナ前に戻って「痛勤」電車で出社、対面での打ち合わせが一日中続く日々が帰ってきました。
そしてみなさんそれを嬉々として受け入れているようです。それくらい、場の支配力が日本では圧倒的なんです。
アメリカにいるとき、一度話題になりました。「日本って相変わらず、対面の打ち合わせが好きだよね」と。リモート会議やメールではダメで対面で打ち合わせをしたがると思われています。これはもう国民性ですね。
野口 聡一
宇宙飛行士
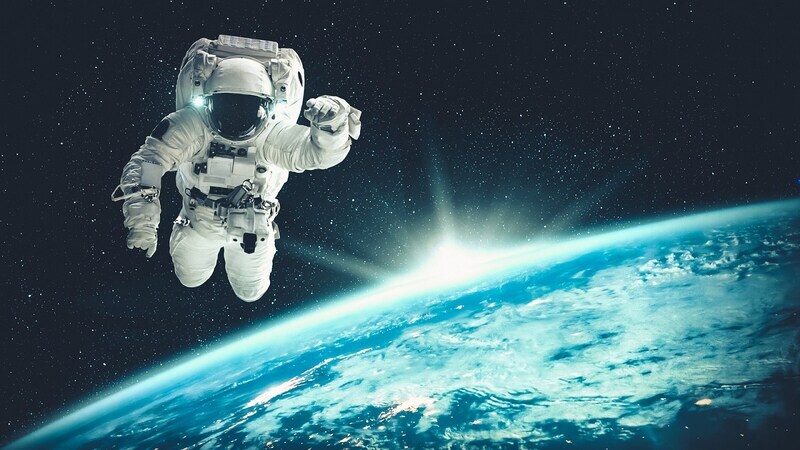


コメント