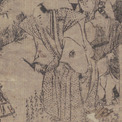
(鷹橋忍:ライター)
早いもので大河ドラマ『べらぼう』も前半の放送が終了した。そこで今回は、主人公・蔦屋重三郎の後半生をご紹介したい。
日本橋へ
天明3年(1783)9月、34歳の蔦重は、日本橋通油町(現在の東京都中央区日本橋大伝馬町)にあった地本問屋・豊仙堂丸屋小兵衛の店を買い取り、日本橋に拠点を移した。
桐谷健太が演じる大田南畝が著した『菊寿草』によれば、丸屋小兵衛は、宝暦10年(1760)に戯作の草紙にはじめて作者名を入れたり、外題の絵を紅摺にしたりしたことなどで知られた版元だったようだ。
なお、吉原の店も、蔦屋徳三郎名義の支店として、『吉原細見』を中心に、営業を継続している(鈴木俊幸『本の江戸文化講義 蔦屋重三郎と本屋の時代』)。
江戸経済の中心地で、書物問屋や地本問屋が軒を連ねる日本橋へ進出したことにより、蔦重は江戸の出版王への道を駆け上がっていく。
自らも狂歌師となり、狂歌ブームに乗る
天明年間(1781~1789)の江戸では、狂歌ブームの絶頂期が到来していた。
この狂歌ブームを商機と見た版元は、天明3年(1783)の正月に刊行された唐衣橘洲(からごろもきつしゆう)編の『狂歌若葉集』(版元は近江屋本十郎など)、桐谷健太が演じる大田南畝(狂名は四方赤良)と浜中文一が演じる朱楽菅江(あけらかんこう)編の『万載狂歌集』(版元は須原屋伊八)の2編をはじめ、著名な狂歌師の編纂する狂歌本を出版していく。
蔦重も狂歌本を出版したが、それだけにとどまらなかった。
「蔦唐丸(つたのからまる)」の狂名を称し、蔦重は狂歌師として狂歌界に身を投じている。
狂歌を嗜む人々は、「連(れん)」と呼ばれるグループを編成して活動していたが、蔦重が所属したのは、吉原の女郎屋・大文字屋の主人である伊藤淳史が演じる二代目市兵衛(狂名は加保茶元成/かぼちゃのもとなり)が率いた「吉原連」である。
自ら狂歌師の仲間入りを果たしたことにより、蔦重は狂歌師たちと交遊を深め、他の版元よりも、圧倒的に優位な立場を勝ち取っている。
蔦重は、狂歌はあまりうまくなかったようだが(鈴木俊幸『本の江戸文化講義 蔦屋重三郎と本屋の時代』)、狂歌を楽しむ場を設けることには長けていた。
趣向を凝らした遊び場を用意して狂歌会を主催し、その場で詠んだ狂歌を書籍化していった。
また、蔦重は狂歌本に浮世絵師による絵を加えることで、新たな書籍ジャンル「狂歌絵本」を作り上げている。
天明8年(1788)に刊行した狂歌絵本『画本虫撰(えほんむしえらみ)』では、虫にちなむ恋の狂歌に合わせて、染谷将太が演じる喜多川歌麿が描いた虫と草花の絵が大評判となり、歌麿の出世作となっている。
ベストセラーと引き換えに、朋誠堂喜三二と恋川春町を失う
順調な発展を遂げてきた蔦重の出版業だが、渡辺謙が演じる老中・田沼意次が失脚し、天明7年(1787)6月に老中首座に就任した寺田心が演じる松平定信が、いわゆる寛政改革を主導すると、大きな痛手を受けることになる。
質素倹約と文武奨励を強く掲げた寛政改革の下では、窮屈な雰囲気が広がり、人々は不満を募らせていった。
これはチャンスとばかりに、蔦重は寛政改革を揶揄する二つの黄表紙を世に送り出す。
天明8年(1788)には朋誠堂喜三二作の『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくとおし)』を、寛政元年(1789)には岡山天音が演じる恋川春町(倉橋格)作の『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』を刊行した。
朋誠堂喜三二作の『文武二道万石通』は、時代設定こそ鎌倉時代であるものの、定信の改革を茶化したものだとたやすく想像できる内容で、大ヒットを飛ばした。
『文武二道万石通』の大ヒットを受けて刊行されたのが、恋川春町作の『鸚鵡返文武二道』である。
舞台は平安時代で、定信がモデルとされる菅秀才(菅原道真の子)が武を奨励したところ、武勇の競い合いが行き過ぎ、騒動が生じた。
そのため、文を奨励して聖人・賢人の教えを講じると、教えを勘違いして凧上げが流行し、鳳凰も出現するという内容だ。タイトルは定信が著した教諭書『鸚鵡言(おうむのことば)』を意識したといわれる。
こちらもベストセラーとなった。
ところが、政治という触れてはいけない禁断の木の実を黄表紙に持ち込んだ(松木寛『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』)代償は、大きかった。
秋田藩士・平沢常富である朋誠堂喜三二は、幕府の目を恐れた藩主・佐竹氏の藩命により、黄表紙などの執筆から退いた(手柄岡持の狂名で、狂歌などの文芸活動は続けた)。
小島藩士・倉橋格である恋川春町は、寛政元年4月に、主家を通じて定信から江戸城への出頭を命じられた。
春町は病気を理由に出頭を辞退した後、同年7月にこの世を去っている。おそらく自害だとみられている(諸説あり)。
蔦重は朋誠堂喜三二と恋川春町という、二人の人気黄表紙作家を失ったのだ。
さらに蔦重にも、筆禍が迫っていた。
出版取締令に違反
寛政2年(1790)、改革の一環として、町奉行所から5月に書物問屋仲間、10月に地本問屋仲間、11月に小売・貸本屋に対して、出版取締令が発せられた。
これにより、好色本は絶版。書物や草双紙などの新規出版が禁止となり、どうしても出版したい場合は町奉行の許可を得なければならないなどが定められた。
この取締の効果を上げるための見せしめとして摘発されたのが、蔦重と、古川雄大が演じる絵師で戯作者の山東京伝(北尾政演)だといわれる(今田洋三『江戸の本屋さん』)。
寛政3年(1791)正月に蔦重のもと刊行された山東京伝の3冊の洒落本(遊里小説)『仕懸文庫(しかけぶんこ)』、『錦之浦』、『娼妓絹籭(しょうぎきぬぶるい)』が、風俗や秩序を乱すと認定。出版取締令に違反するとされたのだ。
3冊の洒落本は絶版となり、山東京伝は手鎖50日(両手に手鎖をはめ、自宅謹慎)。蔦重は、身上に応じた重過料(罰金刑)に処せられた。
蔦重は財産の半分を没収されたといわれる(松木寛『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』)。
写楽の登場
重過料に処せられた寛政3年(1791)の3月には、蔦重は書物問屋仲間に加盟し、専門書・学術書の出版も手がけていくようになる。
寛政改革の文武の奨励により、学術書等の需要は高まっていた。
また、寛政4~5年(1792~1793)にかけて、蔦重は喜多川歌麿の『婦人相学十躰』、『婦女人相十品』、『歌撰戀之部』などの美人大首絵を刊行し、大好評を博している。特に、『婦女人相十品』の「ホッピンの娘」は有名である。
さらに歌麿は、のちに「寛政三美人」と称される、実在する江戸で評判の美人を名入りで描き、大衆から圧倒的支持を受け、一躍、浮世絵界のスターの座に上り詰めた。
寛政6年(1794)には、蔦重は謎の浮世絵師・東洲斎写楽をデビューさせている。
写楽の正体には諸説あるが、近年では阿波国徳島藩主・蜂須賀氏お抱えの能役者である斎藤十郎兵衛とする説が有力である。
写楽は僅か10カ月の間に、140点を超える役者絵や相撲絵など残し、浮世絵界から姿を消した。
最後の最後まで蔦重らしく
寛政8年(1796)、蔦重は脚気を患い、病床に伏している。
寛政9年(1797)になっても快癒することはなく、5月6日、危篤状態に陥った。蔦重は48歳になっていた。
自身の死が迫っているのを悟った蔦重は、「自分は正午に死ぬだろう」と予告。蔦重亡き後の蔦屋について番頭たちに指示を出し、妻と別れの言葉を交わした。
しかし、予告した正午を過ぎても、蔦重が息絶えることはなかった。
すると、蔦重は「自分の人生はもう終わったのに、命の幕引きを告げる拍子木(ひょうしぎ)が、まだ鳴らない。遅いではないか」と、周囲の人々に笑いかけたという。
人生を歌舞伎舞台にたとえた(安藤優一郎『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』)、蔦重らしい粋な言葉を残すと、静かに目を瞑り、夕刻に息を引き取った。
ドラマではどんな蔦重が描かれるのか、見届けたい。
[もっと知りたい!続けてお読みください →] “蔦重”こと蔦屋重三郎が現代日本にのこしたもの、吉原を「流行の発信地」、遊女を男女問わず「あこがれの存在」に
[関連記事]
『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』主人公・“蔦重”蔦屋重三郎はどんな人?吉原のガイドブック『吉原細見』が市場独占
『べらぼう』蔦屋重三郎の「ほんとうの評価」とは?47年の生涯をたどる略年譜



コメント