
●『真夜中の嵐』初顔合わせ時の衝撃
注目を集めるテレビ番組のディレクター、プロデューサー、放送作家、脚本家たちを、プロフェッショナルとしての尊敬の念を込めて“テレビ屋”と呼び、作り手の素顔を通して、番組の面白さを探っていく連載インタビュー「テレビ屋の声」。今回の“テレビ屋”は、制作会社・いまじん社長の中山準士氏だ。
駆け出しの頃の嵐や『ザ・ノンフィクション』の取材対象がスターになっていくのを目の当たりにしてテレビの力を感じ、「面白いものより、見たいもの」「後味の悪いものにしない」という意識で、『行列のできる相談所』や『1周回って知らない話』など、様々なヒット番組を制作してきた同氏。一方で制作会社の経営者としての顔も持つが、メディア環境が大きく変化する今をどのように捉えているのか――。
○ボロボロだった「珍獣ヌーンヴァンヴァ」でのディレクターデビュー
――当連載に前回登場した日本テレビの内田秀実さんが、中山さんについて「会社の社長でありながら、バラエティのディレクターとして第一線で活躍していて、すごいバイタリティだなと思いながらいつも一緒に仕事をしています」とおっしゃっていました。社長業とディレクター業は、今どれくらいの割合ですか?
半々ですね。社長になって4年目に入ったのですが、当初からディレクター業も続けると決めていました。『行列』が3月で終わってからは、特番や配信系や新規の企画をやっています。マネジメントは番組作りより大変なんですが、周りのスタッフが本当に優秀なので、半々の割合でできています。本当に感謝しかないです。
――社長業のお話はまた改めて伺いたいと思うのですが、この業界はどのような経緯で目指したのでしょうか?
大学時代、体育会のサッカー部に入ってプロサッカー選手になりたかったんです。澤穂希さんの旦那さんの辻上裕章(元ベガルタ仙台・現福島ユナイテッド副社長)はチームメイトで親友なんですけど、自分のレベルはそんなところに達していなかったので諦めたのですが、特にやりたい仕事もなくて。そんな中、父親がテレビ好きだったので、テレビ業界も面白いかなあと思ってたんです。
2000年頃の当時は、放送作家という職業がすごく注目を浴びていたんですね。高須(光聖)さんや、おちまさとさんなどが表に出て活躍している時代だったので、放送作家になろうと。なんか「作家」ってカッコいいじゃないですか(笑)
――大御所になれば「先生」と呼ばれますし。
でもなり方が分からなかったんです。そこでテレビ局にいる先輩に聞いたら、制作会社に入って番組に配属されたら、会議に放送作家が4~5人必ず来るから、そこで弟子入りすればいいと言われて、あいうえお順で制作会社を受けました。
――「い」まじんは早いですね(笑)
僕を採ってくれた当時のいまじんの柏井(信二)社長は「うちの会社は何でもやっていい」と言ってくれたので、それを拡大解釈して、「いまじんは放送作家にしてくれるかもしれない」と思って(笑)。内定をくれたのも一番早かったので決めました。
――入社されてADさんからのスタートだと思いますが、最初に就いた番組は何ですか?
『ヤミツキ』(中京テレビ・日本テレビ系)というテリー伊藤さんと郷ひろみさんが出ていた深夜番組です。テリーさんは出演者ですけど、元々ディレクターですから、結構企画に対してダメ出ししていました。その番組の放送作家は、そーたにさん、都築浩さん、鮫肌文殊さんといった錚々たるメンバーで、「まさに神から与えられた現場だ!」と思って会議に行って、作家さんの書く企画書を「面白いなあ、こういう感じなのか」と見ていました。
でも会議が始まると、総合演出と呼ばれるディレクターが、作家さんの出した企画を「これは面白い」「これやってみよう」と瞬時に判断していくんですよ。それを見て、番組を統括するすごい仕事で面白そうだなと心変わりして、今に至ります。
――『ヤミツキ』は2001年3月で終了しました。
その後、『真夜中の嵐』という嵐の日本テレビの初めてのレギュラー番組が立ち上がるということで、チーフADとして入りました。嵐とスタッフの初顔合わせの時に、部屋に入ると櫻井翔くんが起立して「僕たち何でもしますので、厳しくご指導ください!」と言ったんですよ。タレントさんで、ましてやあの大きな事務所で将来を約束されたような5人がそういう姿勢なんだと衝撃を受けて、すごいなと思ったのを覚えています。
――この番組で、ディレクターデビューでしょうか。
はい。『真夜中の嵐』は、真夜中の日本で何が起きているかというのを自転車で北上しながら突撃していく番組で、演出の東井文太さん(日本テレビ)と高谷和男さん(現在はHuluを運営するHJホールディングス社長)にロケの仕方とか構成の作り方や編集の仕方を教えてもらって、ディレクターとして最初に担当したのは二宮(和也)くんの回でした。那須高原で夜になると変な鳴き声が聞こえてくるという話を聞いて、「那須高原に潜む…珍獣ヌーンヴァンヴァを捜せ!」という企画でしたが、ロケも編集も全然うまくいかなくて、ボロボロでした。
○バラエティを担当しながら『ザ・ノンフィクション』も制作
――そんなスタートから、最初に手応えを感じた仕事は何ですか?
当時の柏井社長から「中山はドキュメンタリーもやりなさい」ということで、3~4年目の頃に『ザ・ノンフィクション』(フジテレビ)を1人で作れと言われたんです。僕はドキュメンタリーをそんなに見ていなかったので躊躇(ちゅうちょ)したんですが、六本木のホステスに1年間密着して、これが面白かったんですよ。主人公の一人が小雪さんという中国人の方だったんですけど、その放送の反響をきっかけに人気ホステスになって、テレビに出るようになって、ビジネスも始めて、大成功を収めていくんです。
嵐もそうだったんですけど、スターになっていく人を見れる景色は面白い仕事だなと思ったのと同時に、人の人生を左右する仕事でやっぱり生半可な気持ちじゃダメだと思いました。
――バラエティとドキュメンタリーを並行して作ることで、相互に作用することはありましたか?
根本は一緒だなと思いました。ドキュメンタリーをやってる人はバラエティも作れるし、バラエティをやってる人はドキュメンタリーも作れる。『真夜中の嵐』は、ドキュメントバラエティみたいな番組でしたし、あの時に柏井社長が「大丈夫だからやれ」と言っていた意味が分かって、すごく大きな経験でした。
その後、テレビ東京で『世界を変える100人の日本人! JAPAN☆ALLSTARS』という番組を担当しました。世界で活躍する日本人を紹介するという内容で、どういう人生をたどって今に至るのかを深掘りしていくので、これもドキュメンタリー要素があったんです。やっぱりすごい人はとても謙虚で、そういう立場になっただけの理由が分かるんですよね。
●島田紳助『行列』降板のピンチで言われた「ラッキーだな」
――3月に終了した『行列のできる相談所』(『行列のできる法律相談所』から改称)には、長年携わってこられましたよね。初代司会者の島田紳助さんをはじめ、レギュラーの方が突然降板してしまうというピンチを何度も乗り越えた番組でした。
紳助さんが引退された直後が、僕の担当回だったんです。引退会見するというのをその日に知って、ちょうどその週が収録日だったんです。どうすればいいのか何も思い浮かばないし、まだ30歳くらいだったので、もう真っ青でした。
それで総合演出の高橋利之さん(日本テレビ)に会いに行ったら、「お前は人の経験できない場面でやれて、ラッキーだな」と言われたんです。僕の知らないところで高橋さんをはじめ、いろんな方が対応に追われいてたと思うんですけど、150人くらいいる『行列』のスタッフに対しては、落ち込むとか下を向くとか、そういう姿勢は全く見せないので、その言葉を聞いて「やれるだけのことをやろう!」とスイッチが入った記憶があります。
――高橋利之さんは、日テレ制作者の皆さんが影響を受けていますよね。『行列』の作家だった石原健次さんは「長嶋茂雄さんみたいな人」とおっしゃっていました。
そうなんです。周りにいる人はみんな高橋さんの求心力に惹かれ、知らずに戦闘力が上がっていくような感じがあります。
――中山さんは『行列』最終回の3時間生放送の演出も担当されましたが、どんな思いで臨まれたのでしょうか。
これだけ注目される番組の最終回を、仲間と一緒にできるのは幸せだなと思ってやってました。後ろ向きな気持ちは本当になくて、楽しくやりたいなっていう感じでした。
――クライマックスは、カンボジアで小学校を設立する「カンボジアプロジェクト」のオークション企画でしたが、紳助さんの過去映像も流れました。
カンボジア企画を立ち上げた方ですし、今聞いてもすごく芯の通ったことをおっしゃってるんです。「偽善者でもいい。やらないよりやったほうがいい」というメッセージは、絶対に伝えたいと思いました。
○50年前に会った人も印象が変わらない明石家さんま
――『行列』チームでは、『誰も知らない明石家さんま』も制作されていますよね。
さんまさんが60歳を迎える時に、各局でさんまさんの還暦特番をやったのですが、それがもう10年続いているんです。全くネタが尽きません。さんまさんは打ち合わせでも、本当にテレビのままで誰とも隔たりなくお話しされますし、街で出会った人もみんなイメージのままだと言いますよね。もっとすごいのは、50年前にさんまさんに会った方も「面白い」「ずっとしゃべってる」「いい人」と同じことを言うんですよ。ずっと第一線でやられているのは、やっぱりすごいですよね。
僕は自分のことを凡人だと思うのですが、すごい人を見てきた人生ではあると思うんです。さんまさんもそうですし、高橋利之さんもそうですし、『世界を変える100人の日本人』に出てくれた方々もそうです。そこに共通しているのは、もちろん魅力的で人が集まってくるんですけど、偉ぶらなくて誰に対しても平等なんです。年齢に関係なく、誰よりも努力していて、かつみんなに優しい。そういう人たちからいろんな影響を受けて、すごく恵まれているなと思います。
●「なんで離婚しないの?」に答える佐々木希の覚悟
――番組作りにおいて、共通して意識されているのはどんなことですか?
一つは、「面白いものより、見たいもの」です。もちろん面白いものを作るのは大事なんですが、まずは見てもらわないと全く意味がない。僕らの仕事は、見てくれる人がいないと存在価値がありません。もう一つは、人を嫌な気持ちにさせない、「後味の悪いものにしない」ということ。この二つはすごく考えています。
――7月2日には、当連載に前回登場された内田さんと一緒に作っている『1周回って知らない話』のスペシャルがありますが、ゲストが佐々木希さんですね。
「今どきの視聴者が知らない疑問を本人に直接ぶつけて明らかにする」という番組なのですが、佐々木希さんに聞きたいことを普通の番組で考えると、「なんでそんなにキレイなの?」とか「仕事はいつまでやるの?」とか、オブラートに包んだ質問になりますよね。でも、本当に聞きたいことって何だと思いますか?
――それはもう、夫の渡部建さんとの関係ですよね。
そうなりますよね。今回は、「なんで離婚しないの?」という質問をぶつけてるんです。佐々木希さんと打ち合わせをしたら、「今回は覚悟を決めてきたので、全部しゃべります」と言ってくださって、すごい方だなと思いました。
それで実際に視聴者の疑問をぶつけてみたら、「離婚しないとは決めてないです」「まだ考え中です」と言うんです。ただ、お子さんにとって父親であることは変わりないですし、その子が将来、ネットに残っている情報を見て、自分の父親がどういうことをしたのかを知る日がいずれやって来るので、そんなものは隠せない。それは別れたら消えるものでもないというのを考えた時に、一度結婚して家族になると決めた以上、現状の選択をしたんだと聞いて、強い方だなと思いました。
その中でもリアルだなと思ったのは、「私がここで“許しました”とか“夫婦円満を目指します”とか言ったら、“我慢強い女性だ”とか“カッコいい”とか思われるかもしれないですが、それは嫌です」と言うんです。それが世の中の女性がすごく共感できそうで、素晴らしいなと思いました。切り口は下世話な質問ではあるんですけど、先ほど言った後味の悪いものにしたくないという思いがあるので、佐々木さんが本音を打ち明けられて、いい放送になるなと思いました。
○本音を引き出す東野幸治の優しさ
――なぜ『1周回って知らない話』で、そこまで本音を語る決意をされたのでしょうか。
それはMCの東野幸治さんの存在が大きいと思います。渡部さんが謹慎になった時に、ご自身のYouTubeに出したりして、一番手を差し伸べているのは東野さん。『行列』では「人の心がない」なんてキャラクターを誇張していたので、これは営業妨害になってしまいますが(笑)、東野さんってめちゃくちゃ優しいんです。その感謝が、佐々木希さんにもあるのではないかと思います。
――『1周回って――』は、ゲストの皆さんが本音を語る番組ですよね。
滝沢秀明さんもそうでした。当時バリバリのアイドルでしたが、東野さんとのトークで「将来の夢は?」と聞かれて、「裏方になりたい」と言ったんですよ。だから引退するというニュースを見た時に、本当だったんだと思って。
杏さんも「女優業をやりながら女手一つで子育てできるの?」という疑問に、「そんなの無理に決まってるじゃないですか。めちゃめちゃシッターさんに任せてますよ」と答えたんです。佐々木希さんと同じように、カッコいいなと思いましたね。
――内田さんは、高嶋ちさ子さんファミリーの密着が、ご自身にとってターニングポイントになったとおっしゃっていました。
あのシリーズはすごいですよね。ダウン症のお姉さんに「この人訳わかんないのよ」と言ったり、90歳のお父さんに「うるさい!」と言ったりして、僕は正直、最初はこれを放送していいのかなと思って、ドキドキしながら放送に臨んだのを覚えています。結果、ものすごい反響で、ダウン症の子を持つ親御さんから「とても感動しました。よく放送してくれました」とか「うちも一緒です。ダウン症だからかわいそうだね、大変だねと言われるのは嫌なんです」といった声が寄せられたんです。
SNSで当事者でない人が何か言ってるかもしれませんが、放送にあたっては制作側の一方的な思いを入れず、本当に客観的に家族のリアルを出したので、それが伝わったのだと思います。先ほど言った「面白いものより、見たいもの」って、まさにこれだと思うんです。面白いものを作ろうとすると、どうしても作り手の気持ちが入り過ぎちゃうので。
●世界に発信できる「一撃世代」への期待
――制作会社の社長という立場で、地上波テレビの広告市場が縮小する一方、動画配信サービスが台頭するこの流れは、どう捉えていますか?
これはチャンスだと思います。社員全員と毎年面談しているのですが、若い世代のスタッフが本音でうらやましいです。世界に自分のコンテンツを発信できる環境がどんどん広がっていく彼らを、僕は「一撃世代」と呼んでるんです。見る景色も経済力も一撃で変わる可能性があって、いまじんが蓄えてきたものをそのために投資することもできるので、本当にうらやましい世代です。
例えば、アイドル好きの社員が、そのアイドルのマネージャーに交渉して、イベントや映像を作ったりしているんですけど、そのアイドルが新しい学校のリーダーズみたいに化ける可能性もあるわけじゃないですか。そうやって成功した社員は、契約の仕方も変えていかなければいけないですよね。これからは圧倒的なコンテンツを作ったら、それに見合う対価をきちんと支払うべきだと思いますし、そういう人がどんどん出てきてほしいです。
――そのために、積極的に企画が出せる環境を整備されているのでしょうか。
そうですね。映像化は無理だと言われていたHuluのドラマ『十角館の殺人』を立ち上げたプロデューサーも、原作者のいる京都まで通って信頼を勝ち得ました。そうやって、自分の好きなものを企画にして形にしていくのを見ると、すごいなと思うし、そういうスタッフがいっぱいいると会社としても強くなっていく。クリエイターとして個人の名前を売ってほしいけど、うちは組織力という面でも自信がありますし、いまじんブランドを今後も大きくしていきたいので、そのバランスを見ながら考えていきたいですね。
○「あれはテレビ芸術」さんま×紳助伝説の生トーク
――ご自身が影響を受けた番組を1本挙げるとすると、何でしょうか?
昔、『27時間テレビ』(フジテレビ)の深夜のさんまさんのコーナーに、紳助さんが出たことがあったじゃないですか。あれは本当にすごいと思いました。生放送で本当に言っちゃいけないことをギリギリ避けながらの2人の掛け合い。あれはテレビ芸術ですよね。
――双方の攻守のターンがあって、互角に戦ってる感じがしびれました。
そうそう! しかも、あれ絶対台本ないですから。僕らが書くスタジオ台本って、収録でその通りにいくと面白くないんですよ。やっぱり台本に書けないことが起こると、その放送がハネるので、まさにそんな放送でしたよね。
――いろいろお話を聞かせていただき、ありがとうございました。最後に、気になっている“テレビ屋”を伺いたいのですが…
ABEMA第二制作局長の古賀吉彦さんです。弊社もABEMAさんとはいろいろお仕事をさせていただいてますが、近年見たコンテンツで個人的にワクワクしたものが、ABEMAの『1000万円シリーズ』(『亀田興毅に勝ったら1000万円』『朝倉未来に勝ったら1000万円』など)です。あれこそ先ほども申し上げた「見たいもの」だと思います。古賀さんは『1000万円シリーズ』以外にも、『72時間ホンネテレビ』や、恋リアの『オオカミ』シリーズ、2022年のカタールW杯を手がけていたりと、すごいなと思います。
第一印象は「若いのにスマートに会議を仕切る方だなあ」でした。我々の業界では、よく最初の会議だけ「威勢よくかます人」がいるんですが(笑)、そういうものが全くなく自然体で、これからのエンタメ業界に必要な“華”のある人だと思います。
次回の“テレビ屋”は…
ABEMA第二制作局長・古賀吉彦氏
(中島優)
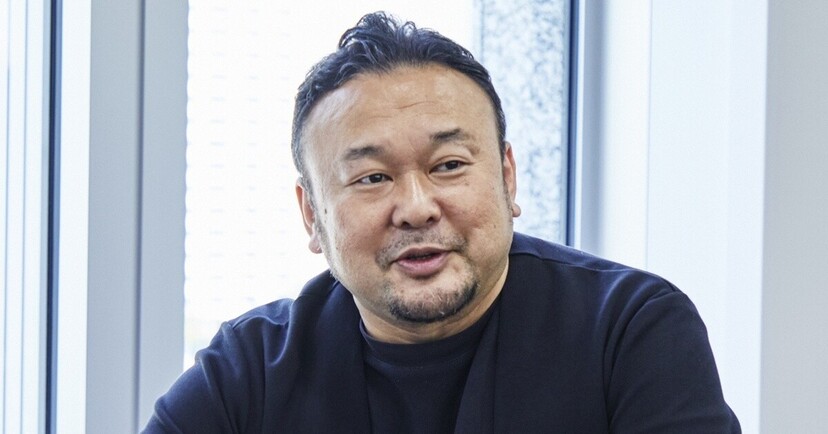


コメント