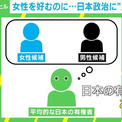

3日午後5時、参院選の立候補が締め切られ、選挙区と比例代表あわせて522人が届け出た。うち女性候補は152人で、これは人数・比率ともに過去2番目の多さ・高さとなっている。
そんな中、日本の選挙に関する最近の研究で日本の有権者に、ある傾向が存在することが明らかになった。それは、平均的な日本の有権者は女性候補を好む傾向があるにもかかわらず、「女性候補は男性候補よりも当選しにくい」と認識しているということ。
実際にこの研究を行った一人である、明治大学政治経済学部の専任講師・加藤言人氏に、詳しい話を聞いた。
「研究では『コンジョイント実験』をした。コンジョイント実験とは、2人の政治家のプロフィールを見せ、どちらの政治家の方がいいか選んでもらう実験。質問の内容を2種類、別の回答者に割り当てた。一つの群では『どちらの候補者のほうが望ましいか』と聞き、もう一つの群では『どちらの候補者のほうが選挙で勝利しそうか』と聞いた。結果を見ると、『望ましいか』と聞かれた場合は、有権者は『女性候補者の方が男性候補者よりも望ましい』と答える確率が高いと分かったが、逆に『どちらのほうが勝利しそうか』と聞くと、その傾向が逆転し、『男性候補者のほうが女性候補者よりも勝利しそうだ』という認識をしていると分かった」(加藤言人氏、以下同)
「世論調査の平均値としては、女性候補者が好まれているから他の人の『勝利しそうか』という質問でも、ゆがみなく認識しているとすれば当然、女性候補者のほうがやや好まれているという傾向が現れるはず。しかし、それが現れずに、平均的な有権者が『自分は女性のほうがやや好ましいと思っているが、他の人たちは平均的に男性のほうが好ましいと考えているのでは』という認識をしていることが分かった」
女性候補が望ましい⇔勝ちそうなのは男性 “思い込みのズレ”女性やリベラル層に強く表れる?

有権者が「個人的に望ましいと思う候補」と「選挙で勝ちそうな候補」との間に起こる考えのズレのことを、研究の中では「選好―期待ギャップ」と呼んでいる。この差は、リベラルな思想を持つ人、そして女性のほうにより強く表れたと話す。
「ジェンダーに関してより保守的な価値観を持っている人と、よりリベラルな価値観を持っている人の中での『選好―期待ギャップ』の傾向の差を見たところ、選好に関してはやはりリベラルな人のほうが、より女性候補者を好む傾向が見られたが、『期待』のほうに関しては差が見られない。ギャップの観点でいうと『選好―期待ギャップ』というのは、よりジェンダー的にリベラルな価値観を持つ人のほうがよりギャップが大きいことが分かった」
「あとは性別でも分けて分析をしたが、性別の結果が非常に興味深い。これは意外だったが、男性よりも女性の回答者のほうが女性の候補者を好みやすいというのは、期待されている傾向として現れたが、どちらが勝利しそうかという質問を聞いたときに、実は男性回答者よりも女性回答者のほうが、女性が勝ちにくいと思っている傾向がこの研究では見られた」
この研究は、女性が増えにくい日本の政治の背景に、「戦略的差別」があることを示唆しているという。
戦略的差別とは、選挙で、ある候補を好ましく思っていても、その候補が当選する可能性が低いと認識した場合、代わりにより当選が期待される別の候補の支持や支援をすること。
「勝ちやすい候補者に投票することで、自分の一票を無駄にしないという行動を取る有権者のことを、戦略的差別を行っているという」
「戦略的差別」の背景に「勝つのは男性」の思い込み?

加藤氏の研究グループは、今回明らかになった有権者の「思い込み」の傾向が「戦略的差別」の行動の背景にあると考えている。
研究の結果から、世界的に見て、日本が不平等な価値観や意識を持っているわけではないと話す加藤氏。これからの選挙や投票における、今回の研究の意義を強調した。
「例えば、この人は女性だから票が集まりにくいのではと思って、その人への投票や支援をためらう必要はないし、実は自分が思っているよりも良いパフォーマンスを出すかもしれない。それは候補者のリクルートメントの段階でも同じように、自分が思っているよりも実はより有権者に支持されているかもしれないと認識するだけでも、この研究の意味があるのではないかと思っている」
この研究結果にニュース番組『ABEMAヒルズ』のコメンテーター、精神科医でスポーツメンタルアドバイザーの木村好珠氏は「納得」と話す。
「実際、何年も前から女性が活躍すると言われている。男女共同参画社会基本法は、そもそも1999年の話。もう26年という月日が経っているので、この政治の世界は女性の活躍は遅れているイメージ。新しい内閣ができたときに、女性が多いなというイメージはあまりない。本来であれば、少なくとも40%はいてほしい。それがまだそこには至らない。むしろ数えられる程度というのは、政治の社会の遅れ」(木村好珠氏、以下同)
今回の研究では、戦略的差別につながっている可能性があるというが、木村氏は次のように分析する。
「心理学の中でも“アッシュの同調実験”というものがある。正解、不正解がわかりやすい問題を、サクラを入れてどっちが合っているかと質問をしてみる。不正解のほうに、サクラ側が全員正解だと手を挙げると、正解がどちらかは明らかなのに、人々が不正解のほうを選ぶという実験。人間の心理は、こっちのほうが正しいよねと思ったとしても、大勢の人が賛同した方が正しいのかなと同調してしまうというのは基本の心理にある」
「思い込み」は有権者だけではなく、政党側にも?

さらに、研究チームは今回の結果を受けて、思い込みは有権者だけではなく、候補者を選ぶ政党側にも生じている可能性があると指摘。この指摘に木村氏も「可能性はあると思う」という見解を示した。
「有権者が見ているのは男性の政治家が多い。アンコンシャスバイアスという無意識的な思い込みが働くので、自分が生きてきた中で見てきた政治家は男性が多いとなると、頭の中に『政治家=男性』という方程式ができてくる。そうなると、リクルートする側もなんとなく男性が政治家になっているイメージがあるから、男性のほうが通りやすいよねという印象があり、男性を選びがちになってしまう」
では、アンコンシャスバイアスを取り除くためにはどういったことが大事になってくるのか。
「人間はモデルケースを見ていると、あたかもできるような気になってくる。最初に出てくる人がすごく大切になってくる。今の時代、活躍している女性が少しずつ出てきているので、その人たちがSNSなどで『こうやって活躍しているよ』という情報を出していくのはすごく大事。『私にももしかしたらできるかも』と感じることが大切なので、そういった情報を今現役でやっている人が実際にSNSなどで発信していくと、少しずつバイアスは変わると思うし、バイアスを自分自身で自覚することも大事なこと」
(『ABEMAヒルズ』より)
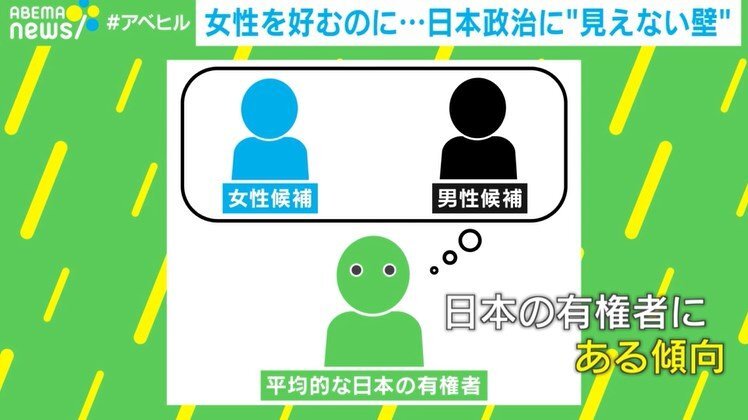


コメント