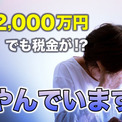
配偶者が亡くなった際、相続税の税制優遇措置として「配偶者の税額軽減」という優遇規定があります。同制度は「1億6,000万円」もしくは「法定相続分」のどちらか多い額まで相続税がかかりません。しかし、適用要件を注意しなければ「多額の追徴税」を支払うハメに……。宮路幸人税理士が具体的な事例をもとに「配偶者の税額軽減」のしくみと注意点を解説します。
相続財産が「1億超」も非課税に…相続税の優遇制度
相続税には「配偶者の税額軽減」という優遇規定があります。これは、配偶者が相続した財産について、法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い金額までであれば、その配偶者には相続税がかからないというものです。ほとんどの場合、夫婦間の相続はこのどちらかの範囲に収まるのではないでしょうか。
たとえば、亡くなった夫に10億円の財産があった場合、残された妻の法定相続分は5億円です。よってこの場合、5億円まで相続税がかからないということになります。
このように、配偶者の税額軽減は非常に強力な相続税の優遇制度といえるでしょう。
ただし、下記のケースでは「配偶者の税額軽減」を適用することができないため注意が必要です。
1.「未分割」の相続財産
同制度は、遺産分割や遺言により配偶者が「実際に取得した財産」に対する相続税を控除する制度です。そのため、未分割財産は対象外となります。相続税は未分割であっても、亡くなった日から10ヵ月以内に申告書を提出しなければならないため、未分割の場合はこの規定を適用することはできません。
ただし、未分割の申告をする場合でも、相続税の申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、遺産分割が成立したあと、更正の請求を行ったのち、同制度の適用を受けることが可能です。
2.配偶者が仮装隠ぺいした相続財産
また、仮装隠ぺい行為により申告漏れとなった財産に呼応する相続税についても、同制度の適用対象外となります。
「配偶者の税額軽減」を“過信”していた79歳女性の末路
79歳のAさんは、3年半前に夫のBさんを亡くし、同居していた自宅(評価額約1億円)と夫名義の預金2,000万円を相続しました。その後は、わずかばかりの年金とBさんの遺産で細々と暮らしています。
また、Aさんにはひとり息子のCさんがいます。とはいえ、以前から折り合いが悪く長年ほとんど音信不通状態です。Cさんは、父であるBさんの葬儀にすら現れませんでした。
こうしたなか、夫の死から3年あまりが経ち、ようやくAさんが1人きりでの暮らしにも慣れたころ、Aさんのもとに税務署から着信がありました。聞けば、「相続税の申告がまだ確認できていないのですが、現在どのようなご状況でしょうか?」といいます。
しかし、Aさんは“とある理由”から申告が必要ないと判断し、この連絡の重要性を認識しておらず、いつの間にか対応を忘れていました。その結果、相続税の税務調査が行われることに。
税務調査官から告げられた「まさかの事実」に悲鳴
税務調査当日、Aさんの自宅には2人の調査官がやってきました。
調査官が到着するや否や、Aさんは得意げにこう言います。
Aさん「配偶者は1億6,000万円まで非課税なんでしょう? 知っていますよ。前にテレビで税理士さんが言っていたもの。この優遇制度があるから配偶者には相続税がかからないって。わざわざ来ていただいて申し訳ないけれど、夫の遺産は1億6,000万円の範囲内ですから、問題ないはずよね?」
調査官「たしかに『配偶者の税額軽減』という規定はあります。ただ、いずれにせよ相続税の申告が必要です。Aさんは今日まで申告書を提出されていませんよね」
Aさん「えっ…? 非課税なのに申告が必要なんですか!?」
「基礎控除額」を上回る場合は申告が必須
相続財産は「基礎控除額」を下回る場合、相続税の申告も納税も不要です。しかし、Aさんの相続財産は基礎控除額を上回ることから、相続税の申告が必要でした。
■Aさんの相続財産:自宅(評価額約1億円)+夫名義の預金2,000万円=合計1億2,000万円
■基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
Aさんを襲うさらなる悲劇…最終的な「追徴税額」は
また、Aさんは折り合いの悪い息子とは長年連絡をとれていません。そのため遺産分割も行われておらず、相続財産は「未分割」の状態でした。
前述のとおり、未分割の場合「配偶者の税額軽減」は使えないため、いったん法定相続分で相続税の申告と納付を行う必要があります。
その後、申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、後日分割が決まったときに「配偶者の税額軽減」の適用を受けることができます。なお、適用を受ければ手続きのあと相続税を還付してもらうことが可能です。
しかし、Aさんは遺産が「未分割」だったうえに申告書が未提出であったため、この「配偶者の税額軽減」は適用されませんでした。
そのため、相続税約1,200万円に加え、無申告加算税や延滞税など300万円が課されることに。Aさんは、うなだれるしかありません。
「1,500万円!?……年金暮らしなのに、そんな大金払えない……」
Aさんの“無知”と“勘違い”が招いた追徴課税
Aさんは「配偶者の税額軽減」について「よほどの金額でない限り、配偶者の相続税は非課税」と、自分にとって都合の良い部分だけを記憶。その結果、相続税の申告を怠ってしまいました。
前述のとおり、「配偶者の税額軽減」は申告期限から3年以内であれば、期限(相続発生から10ヵ月後)のタイミングで未分割であっても、手続きを行うことで適用が可能です。
しかし、Aさんは未分割の状態で申告を行わず、3年以内という期限も過ぎてしまったことから、適用は難しいでしょう。
「配偶者の税額軽減」の適用には、未分割の状態であっても、とにかく「10ヵ月以内」に申告を行っておくことが重要です。息子さんと音信不通であったとしても、遺産分割は行わなければなりません。
この場合、弁護士に依頼し、裁判所に申し立てるなど、法的に問題のない遺産分割手続きを進める必要があったといえます。
思わぬ追徴課税を避けるために…専門家の力を借りて、確実に申告を
配偶者を亡くすと、自分が想定している以上に気が動転します。また、配偶者の逝去に伴う「諸々の処理」は非常に煩雑であり、よほど事前に準備していない限り、冷静であれば「こんなことあり得ないだろう」と感じるようなミスを犯してしまうことも少なくありません。
今回紹介したAさんも「なんで税務署から電話があったときにきちんと調べなかったんだろう。もっと早く相談していればよかったです」と悔やまれていました。
「配偶者の税額軽減」は、適用されれば相続税額を大きく減らせるものの、正しく理解していないとかえって多くの税金を課される可能性があります。
まずは自信の基礎控除額を把握したうえで、相続税の課税財産が基礎控除額を上回るときは申告が必要となります。判断に迷った際は専門家に相談のうえ、適切に手続きを進めることをおすすめします。
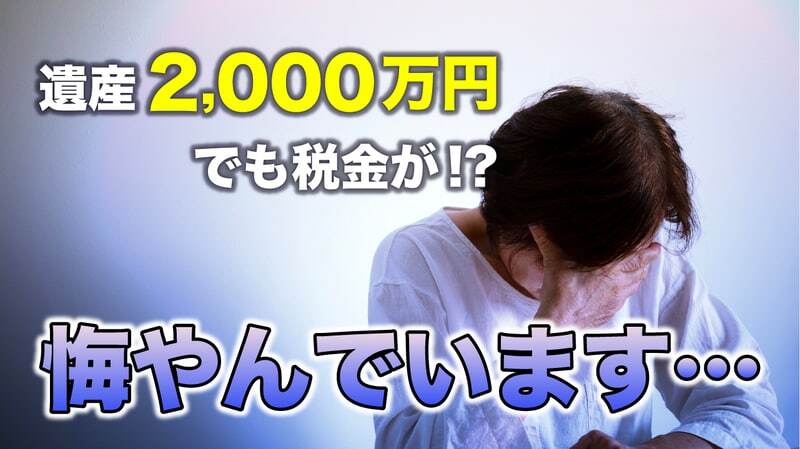


コメント