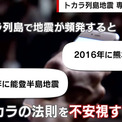

鹿児島県のトカラ列島で発生した震度6弱の強い地震。今回の地震については、これまでに例を見ない現象がいくつか確認されているという指摘もある。そもそも地震についてどこまで解明されているのか、そして何がまだわかっていないのか、専門家とともに考えた。
政府の地震調査委員会は4日、臨時の会合を開いた。そこで報告されたのはこれまでの地震では例をみない現象の数々だった。
「最初のフェーズから、第2フェーズに移ったところで非常に活発になったのが事実。どうして起きたかはまだよくわからない」(地震調査委員会 平田直委員長)
トカラ列島の群発地震は震源が東西に拡大している。震源が東西に分かれることは珍しいとされ、6月の段階から東西に分かれる傾向があったという。はじめは東側が活発だったが、7月に入ってからは、西側でも活動が活発化。そして7月3日、震度6弱の地震が発生したのは、東側の震源域だった。
さらに、平田委員長によると「変動量が極めて大きい。能登半島地震のときですら数年かけて何ミリ、何センチだった。(今回は)2日3日で4センチも動いたというのは非常に珍しい」という。
国土地理院が、人工衛星による観測データを解析したところ、地震が始まった6月21日以降、宝島の観測点は、最初東北東へ1.8センチ動いていた。ところが、7月2日正午から3日午後にかけて、今度は南方向へ4.2センチ移動。方向まで急変したという。
なぜ4センチの地殻変動が起きたのか。トカラ列島の地下で何が進行しているのか。元気象庁長官の西出則武氏は「断層のズレがあって地震が起きていることは、観測技術からわかっている。わからないことは、なんでここで繰り返し群発地震が起きているかということ」と語った。
さらに、西出氏によれば群発地震には様々な「終息」の形があるそうだ。例えば、能登のように、群発地震が続いた先に震度7クラスの地震が起きてしまったケース。長野県松代町では、1965年ころから6万回以上の群発地震が観測されたが、最終的には、地下水が出て終わったという。
では今回の終息はどのような形となるのか。「トカラはこれまで、群発地震がある程度の期間続いて収まることが多かったが、今回は圧倒的に地震の数が多く期間が長いので、これまでと違う終わり方をする場合もある」(西出氏)
今回の地震を巡っては「トカラの法則」という言葉も注目されている。これまでトカラ列島で地震が頻発すると、2016年に熊本で地震、2024年に能登半島で地震が発生するなど、日本のどこかで大地震が起きるというトカラの法則を不安視する投稿も相次いでいる。
「日本は地震国、結び付けようと思えば、結びつく地震が見つかってしまう」「トカラ列島でどれくらいの地震が起こっていたかというのと、結びつけた地震(との関係性)をとってみると、トカラ列島で群発と言えないぐらい数十回とか非常に少ない回数の地震が起こったのと、能登半島地震とか他の地震と関連付けたような資料が出てきた。今回(トカラ列島地震では)1000何百回と起こっているが、それとほんの数十回しか起こらなかったものを同列に比べるのはそもそも変。元々日本は世界有数の地震国であるため、トカラ列島で地震が起こったときに、何カ月かの間、日本全国見回したら、結びつけられるような現象って何かしら起こることの方が多いのかもしれない。そういう目で見ると、そういう風に見える程度じゃないか」(西出氏)
では、現在の科学で地震はどこまで解明され、何がまだわかっていないのか。「東海地震、南海トラフのプレート境界の巨大地震、マグニチュード8の巨大地震を予知したいと気象庁が国をあげて何十年もやってきた。研究すればするほど、社会に役立つような予知はできないことがわかってきた」(西出氏)
(『ABEMA的ニュースショー』より)
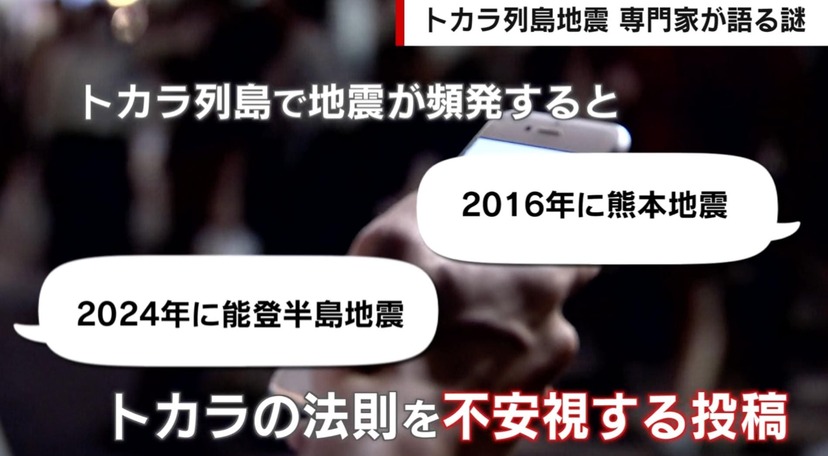


コメント