
社会実装につながる研究開発現場を紹介する「イノベ見て歩き」。第21回は、群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センターの天谷賢児センター長や桐生市の島田良明課長補佐らが開発・運用に関わっている低速電動バスの地域実装の取り組みを紹介する。高齢化や公共交通サービスの縮小といった地域課題を解決することで、持続可能なまちづくりを下支えしている。
CO₂排ガスの削減目指す
流体力学の知見がお役立ち
古くから織物の町として栄えてきた群馬県桐生市。昔の織物工場や土蔵など絹織物に関わる建造物が多く見られ、市の一部は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。この趣ある町並みをゆっくりと走るのが「MAYU」の愛称で親しまれる低速電動バスだ。このバスは、単なる移動手段としてだけでなく、地域の新しいコミュニケーション手段の1つとしても期待されている。
バスの開発は、脱炭素に取り組みながら地域の活性化を目指す、2008年に採択されたJST社会技術研究開発センター(RISTEX)のプロジェクトからスタートした。当初からこのプロジェクトに携わっていた群馬大学の天谷賢児教授は「プロジェクトではさまざまな二酸化炭素(CO₂)削減策を検討・実施しましたが、その中心となったのがCO₂の削減効果が大きい低速電動バスの開発でした」と振り返る。さらに、桐生市では住民の高齢化や人口減少といった地域課題もあり、バスはそれらの解決にもつながる手段だったという。
現在は次世代モビリティ社会実装研究センター長を務める天谷さんだが、元々の専門は環境流体力学。一見、スローモビリティとは無関係に思えるが、流体力学には交通の流れを研究する「交通流」という分野があり、その知見が低速で走るバスが周りに与える影響を調べるのに役立っている。「今は交通流のシミュレーターを使った実験も進めています。今後このバスを導入したいという地域にとって、シミュレーションで低速走行の影響を検証できるのは大きなメリットです」。
乗客の会話が弾む対面式座席
企業やSSH校、住民らも協働
2011年に電気自動車メーカーのシンクトゥギャザー社(桐生市)が開発した10人乗りの低速電動バスeCOM-8は、通常の路線バスとは異なる特長を備えている(図1)。最高速度は時速19キロメートルと非常にゆっくりで安全性が高い。また、側面には窓ガラスがない。天谷さんは「暑さや寒さなど周囲の環境を直接感じられるようなものにしたいと、概念設計を行いました」と説明する。技術面では、タイヤとモーターをユニット化したインホイールモーターを開発。高齢者が乗りやすい低床化を実現できた。大人2人で付け替えられるほど軽量の、交換式のバッテリーも新たに開発。フル充電すれば市内40キロメートルを走行することが可能だ。
もう1つ、このバスには大きな特長がある。それは、乗客同士のコミュニケーションを促す機能があることだ。設計段階からコミュニケーションが取れる空間を目指して座席を対面式にしていたが、実際に運行してみると予想以上に会話が弾んだという。座席間の距離や配置には、空間配置がコミュニケーションや人間関係に与える影響を研究する「近接学」の知見が生かされている(図2)。2016年の運行実験の際には、乗車しない人までバス停に集まり会話を楽しむ光景も見られ、バスをきっかけにしたコミュニケーション活性化という相乗効果も生まれたそうだ。
低速電動バスで地域課題を解決するという取り組み全体に目を向けると、大学や市だけでなく、複数の企業やスーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定校の群馬県立桐生高等学校などが協働していることも大きな特長だ。また、天谷さんが主導し桐生市や地元企業、各種団体などが自由に参加できる会議を、月に1回程度でこれまでに100回近く開催。地域創生に携わる人たちが集まり、情報を共有・交換している。
「MAYU」が桐生市に登場して10年以上が経った。現在は、無料バスとして週末に市内の歴史的建造物や遊園地・動物園を含む3つの観光コースを走っているほか、地域のイベントなどにも貸し出している。また、住民らが運行設計に携わり、病院や商店など行きたい場所を調整しながら走らせる実証実験も続けている。
大学連携推進担当(当時)として、群馬大学と共に長く取り組んできた桐生市役所の島田良明課長補佐は「当初は、低速電動バスが交通の障害物扱いされるのではという懸念もありました」と語る。しかし、桐生市民にとって群馬大学は自分たちの地元の大学という意識が強く、大学と地域で作ったバスであるという意識がある。大学が関わるバスの取り組みに協力的で、応援もしてくれているという。
評価されて全国20カ所に導入
課題は持続性確保、模索続く
2024年10月には、科学技術・イノベーションによって社会課題を解決する取り組みをJSTが表彰する「STI for SDGs」アワードの優秀賞を受賞。地域に根差した住民の新しい交通手段であり、コミュニケーションツールでもある低速電動バスを活用した地域活性化の取り組みは、各方面から評価されている。また、このバスは富山県黒部市の宇奈月温泉など全国約20カ所にも導入されている(図3)。
ただ、バスの地域実装には課題もある。天谷さんが最大の課題と指摘するのは、持続性の確保だ。現在は行政の支援とレンタカー事業などで成り立っているが、行政の支援なしに公共交通のように日々運用することは、経済的に難しいという。そこで解決策の1つとして講習を実施して住民が運転手を担う取り組みを進めているほか、通院用の乗り合いバスとして利用するなど1台のバスをさまざまに活用することなども検討している。
どのような方法が最善なのかまだ結論は出ていないとしながらも、1つの方向性として「ゆるく続ける」という方法があるかもしれないと話す天谷さん。旅客運送事業として常に決まった時間に走るのではなく、例えば住民の合意のもと、ある程度自由に運行する。自分たちで制御できる範囲で管理を行うことで、長く続けられるのではないかと考えている。
島田さんによると、桐生市はこれまでの価値観を転換し、ゆっくりした時間の中で人々が触れ合う社会を理想とする「ゆっくりズムのまちづくり」を提唱していて、その中ではバスの活用も位置付けられているという。利便性の追求だけではない、新たな価値とは何かを探りながら、低速電動バスの地域実装と課題解決の模索はこれからも続いていく。
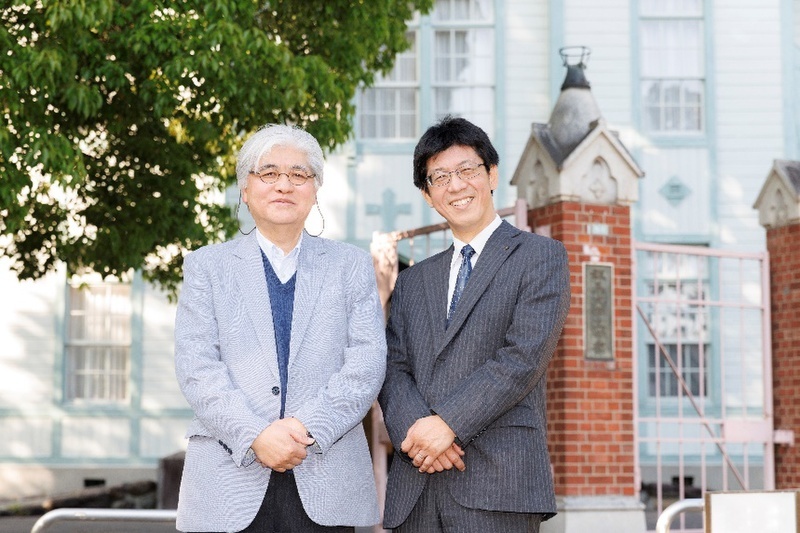


コメント