
1995年、政治的迫害を逃れて来日したイラン人一家4人の代理人を受任したのをきっかけに、難民・入管問題に取り組むようになった児玉晃一さん。
2001年10月の「アフガン難民収容事件」(*1)、入管収容者の死亡をめぐって司法が国の責任を初めて認めた「カメルーン男性死亡事件」(*2)、2021年3月の「スリランカ女性名古屋入管死亡事件」(*3)──。
30年にわたって最前線に立ち続けてきた児玉さんは「当時はバブル期で、どこにでも就職できる状況でした。大学4年になっても進路を決めていなかった自分が法曹界を目指したのは、就職したくなかったからなんです」と、学生時代を振り返る。
努力次第で結果を出せるだろうと覚悟を決めて勉強に集中。2度目の挑戦で合格し、弁護士になって32年。児玉さんにこれまでの歩みを聞いた。(取材・文/塚田恭子)
●消去法で選んだ「弁護士」という道司法試験の勉強中、児玉さんが憧れていたのは裁判官だった。
「"良心に従い、法律にのみ拘束される"という憲法の条文に痺れたんです」
だが、裁判修習で垣間見た裁判官の世界は、企業以上にヒエラルキーが厳しく、理想とのギャップを感じたという。
「検察修習では担当官によくしてもらいましたが、被害者保護の思いが強い検察官は、言葉尻を捉えて供述書をつくるなど、被疑者を黒く染めていきます。『被疑者はそこまで話していません』と伝えても『それをはねのけるのは弁護士の役目だ』といわれました」
消去法で弁護士になったので、かっこいい話はないんです──。児玉さんはそう言うが、法律事務所に入所後、イラン人一家を支援したことが、その後の進路を決定づけた。
「イラン人一家のことを手伝ったのは、友人の関聡介弁護士に頼まれたからで、事務所は外国人問題に特化していたわけではないんです。ただ、ボスは仕事をきちんとしていれば自由にやらせてくれる人だったので、当時は当番弁護や国選弁護なども引き受けていましたし、こうした案件に取り組むこともできました」
●8カ月間で完全に休んだのは1日以来、国際人権法や、諸外国の判例を研究し、自費で海外の収容施設を視察するなど、仲間の弁護士たちと共に制度改善に尽力してきた。印象に残っている事件について尋ねると、児玉さんは少し考えて「アフガン難民収容事件」を挙げた。
「大晦日も深夜2時まで仕事して、弁護団にメーリングリスト(ML)を入れてから初詣用の臨時列車で帰宅しました。元旦だけは実家で酒でも飲もうと思っていたのに、10時頃にMLを見た人から連絡があり、対応していました。
2日も仕事、3日からはまた終電まで仕事。2001年11月から2002年7月までの8カ月間、完全に休んだのは1日あったかどうか。あの働き方は、30代だったからできたのだと思います」
職員による露骨な暴力とハラスメントが横行し、収容環境も劣悪だった東京入管第二庁舎収容場、通称「十条入管」を知る児玉さんは、この間の入管の変化をどうみているのだろうか。
「子どもを収容しなくなったこと、難民申請が入国後60日以内までという制度がなくなったこと。確実に改善されたのはこの2点ですね。十条入管では面会ボランティアが少なく、職員の対応もひどかったですが、今ではさすがに露骨な犯罪行為はなくなりました」
ただ、「それ以外はひどくなっています」と続ける。
「改正入管法の施行から1年、入管は制度変更した直後は批判を避けるために法律を運用しているように見せるので、監理措置制度の下で収容者が早く外に出られているようです。ただ、運用はいかようにも変えられるので、僕は全然信用していません。
法務大臣が5月下旬に公表したゼロプラン(*4)が示すように、入管の目的は強制送還しやすくすることです。最近は訴訟中でも、裁判所から執行停止が出ていなければ、強制送還しています」
国民の安全・安心のために非正規滞在者をゼロにする──。国のこうした方針に対し、児玉さんは「安全が脅かされているという具体的な根拠やデータは示されていない」と指摘する。
「今はヘイトが吹き荒れていますが、大事なのは記号ではなく、生身の人間として外国の人と接することです。一緒にご飯を食べるなど、つながりを持てば、ヘイトはくだらないと思う人が増えるのではないでしょうか」
●証拠映像を法廷で公開するという使命2011年3月の東日本大震災では、被災者支援にも奔走した。
「外国の人が困っているのではと、支援団体の依頼で4月に被災地に行きました。実際には、技能実習生は大使館の手配で帰国していて、家族滞在の人が少し残っていた程度でした。ただ、家族を失い、家を流され、避難所で不自由を強いられる被災者を目の当たりにして何もしないわけにはいかず、しばらく通いました」
避難所では「まず預金を引き出してください」と伝えた。のちのち家の住宅ローン返済が免除されるとしても、引き落とされたお金は戻らないと考えたからだ。
「お金や相続にまつわる話を紙芝居にして伝えるなど、こちらから声をかけてアウトリーチして、被災者が相談しやすい環境をつくりました」
児玉さんの予想通り、国は災害特例によって住宅ローンを減免した。かつて多重債務の相談を多く扱った経験が、被災者の救済に活かされたケースだった。
実務の蓄積はこれまで手掛けてきた入管事件でも活かされている。名古屋入管で起きたスリランカ女性事件で、5時間半にわたる監視カメラ映像が裁判所で公開された経緯を、児玉さんはこう話す。
「カメルーン男性死亡事件同様、映像は間違いなくあると思ったので、国会で議員に質問してもらい、『映像はある』との答弁を得ました。答弁した以上、国は消せないので、あとはどう開示させるかです。証拠保全で映像を確認し『これは判決を書く裁判官に絶対に見てもらわないといけない』と確信しましたが、そのためには法廷で傍聴人と一緒に見るのが一番です。そこで、上映すべきだと裁判所に訴え続けました」
粘り強いやりとりの末、2023年6月21日、ついに名古屋地裁で、5時間半の監視映像が公開された。
人の困難と向き合い、解決に取り組む弁護士の仕事はハードだ。依頼者と同調し過ぎれば、自分が潰れかねない。「真面目で優秀な人がやめていくのを見てきました」と話す児玉さんに、心のバランスの取り方を尋ねると、こんな答えが返ってきた。
「気晴らしは仲間とお酒を飲むことです。最初は『依頼者が苦しんでいるのに飲んでいていいのか』と悩みましたが、全力を尽くしたうえで自分の時間も持つほうが、結局は依頼者のためになると気づきました。それがなければとっくに潰れていたと思うので、自分はお酒が飲めて本当に良かったと思います」
(*1)2001年9月11日、米国でテロ事件発生後、それ以前から在留し、難民申請中だったアフガニスタン人9人が一斉摘発・収容された事件。東京地裁は9人のうち、5人に収容令書発布処分の執行停止を認めたものの、4人は認めないという判決を下した。
(*2)東日本入国管理センターに収容されたカメルーン人男性が、再三体調不良を訴えたにも関わらず、病院で治療を受けられないまま2014年3月に収容施設で亡くなった事件。2025年2月、裁判所は入管職員の救急搬送義務違反を認め、165万円の賠償を命じる判決が確定した。
(*3)名古屋入管に収容中のスリランカ女性ウィシュマ・サンダマリさんが2021年3月6日、収容施設で亡くなった事件。亡くなる3週間前の血液検査で身体が飢餓状態にあったことが判明していたにもかかわらず、適切な医療をしなかった国を相手に現在訴訟が続いている。
(*4)5月23日に法務大臣が「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」を発表。外国人に安全・安心が脅かされているという前提として、具体的な根拠やデータを示すことなく、国が差別を助長するスタンスを取ることに、難民支援団体は懸念を抱いている。
【プロフィール】こだま・こういち/1966年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。1994年弁護士登録。2009年マイルストーン総合法律事務所を開設。『2023年改定入管法解説』『入管問題とは何か 終わらない<密室の人権侵害>』など著書・論文多数。全件収容主義と闘う弁護士の会 ハマースミスの誓い代表、全国難民弁護団連絡会議 世話人などを務める。
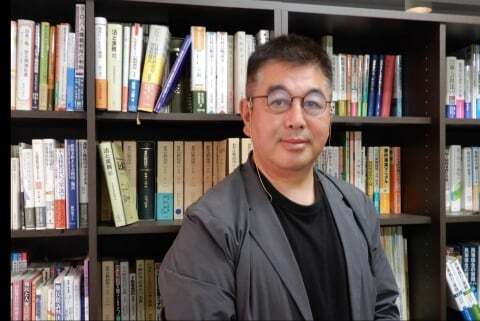


コメント