
ファミリービジネスにとって、経営者の離婚は会社の資産を半減させ、ときには経営権そのものを失いかねない思わぬ経営リスクとなることがあります。この悲劇を回避するための資産防衛術をみていきましょう。本稿では、経営リスクから離婚問題を切り離す手段となり得る「婚前契約」について詳しく解説します。
富裕層の離婚のインパクト
マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツの元妻メリンダ・フレンチ・ゲイツは、離婚と同時にビル・ゲイツの投資会社であるカスケード・インベストメント社から、約18億米国ドル相当の株式(当時のレートで約1,970億円)を取得したと報道されました。アマゾンの共同創業者の一人であるジェフ・ベゾスは元夫人であるマッケンジー・ベゾスに対し、離婚に伴い、約383億米国ドル相当の株式(当時のレートで約3兆9,000億円)を譲渡したとも報じられています。
離婚の場合、子の親権・養育費と並んで、財産分与は重要な論点となりますが、富裕層カップルの場合、ゲイツ夫妻やベゾス夫妻は極端な例とはいえ、財産分与が多額になる傾向があります。ファミリービジネスを営んでいる場合は、離婚に伴う財産分与がファミリービジネスの価値を毀損に直結する場合もあるということです。特に夫婦でビジネスを行っている場合等は、離婚は当該ビジネスにとってその継続が危ぶまれる深刻な問題です。
ファミリーガバナンス契約も財産分与リスクの一助にはなりますが、欧米では、夫婦関係の調整のための特有の仕組みとして婚前契約(prenuptial agreementやprenup agreementといいます)が利用されています。従来から、日本人でも国際結婚をするカップル間では、婚前契約が利用されることもありました。しかし、最近では、日本人同士の夫婦であっても、ファミリービジネスを営むファミリーや、富裕層であるファミリーのメンバーが婚姻する場合、婚前契約を締結したいという依頼が増えてきたように思います。
日本における夫婦財産契約の意味
婚前契約は、婚姻しようとする夫婦が婚姻の前に締結する契約で、主に夫婦の財産関係について取極めたものであり、民法上は夫婦財産契約という制度となります(民法756条以下)。婚前契約は、外国から入ってきた新しい概念のように思われがちですが、実は、民法に定められていた制度なのです。
民法によると、夫婦財産契約で別途定めない限り、夫婦の財産関係は、民法が定める法定財産制によることになります。つまり、夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中に自己の名で得た財産は、その特有財産であるとされます(夫婦別産制。民法762条1項)。また、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されます(民法762条2項)。
つまり結婚後も、特に共有とされる財産以外は各自の個別財産として扱われるということです(米国では、結婚後の財産は特有財産以外は共有[コミュニティプロパティ]とする考え方もあります[カリフォルニア州等])。
婚姻に必要な費用は夫婦で分担し(民法760条)、夫婦の一方が婚姻共同生活を営んでいく上で日常に必要とされる日常家事つき第三者との関係で負担した債務があれば、配偶者は連帯して責任を負うこととなります(民法761条)。
このように夫婦財産契約は、民法上の原則を修正するという点にその意義があります。しかしながら、夫婦財産契約は、従来は日本ではほとんど利用されませんでした。私が、夫婦財産契約を作成し始めた約20年前は、夫婦財産契約を第三者に対抗するためには、婚姻成立までに登記することが必要とされていることから(民法758条1項)、万全を期そうと夫婦財産契約を作成するたびにせっせと登記を行っていました。しかし、登記申請するたびに、登記所となる市区町村では初めて取り扱うケースということで登記完了まで大変な時間がかかりました。
いかに夫婦財産契約が日本で流通していないかを示すものだと思われます。もっとも、特別な事情がない限り、夫婦財産契約は、当事者間で効力を有することで足りるので、最近の夫婦財産契約の案件では、夫婦財産契約の登記申請を行うことはほとんどなくなりました。
夫婦財産契約は、夫婦の財産関係について決めるため、夫婦が離婚する場合の夫婦財産の清算方法を定めることが通常です。婚前契約がなかなか活用されないのは、欧米ほどの契約社会とはいえない日本においては、婚姻前に夫婦財産関係について協議することは心情的に憚られるという日本人の文化があるように思います。
また、民法は、夫婦財産契約の内容について特に限定をしておらず、その内容を自由に決められる契約といえますが、夫婦財産契約については判例等も少なく、実際に離婚等の場面で夫婦財産契約が無効化されるリスクが否定できないことも、日本で夫婦財産契約が利用されない理由であるように思います。
日本における夫婦財産契約の意義
夫婦財産契約が将来的に無効化される可能性が否定できないことから、そもそも夫婦財産契約は制度としてあっても作成する意義がないという論者もいるようです。ただ、私は、富裕層の財産保全対策として、夫婦財産契約を作成する意義はあるものと考えています。離婚の際、清算の対象となる財産には、それぞれの当事者が婚姻前から有していた財産や婚姻後に贈与や相続等によって得た財産等夫婦の協力によって得たという性格が認められない財産は含まれないものとされます。
ただ、離婚裁判において、これらの清算対象除外財産と清算対象財産を明確に区別できない場合は、裁判所はまとめて清算対象財産として認定する可能性が高いといえます。清算対象外財産であることの立証責任は、それを主張する者にあるからです。
したがって、婚前財産が多い場合は、婚前財産を夫婦財産契約で列挙し、婚姻後、当該財産から得られる運用益も清算対象外財産として取極め、これらを清算対象財産とは分別して維持管理等することが夫婦財産契約の意義といえると考えています。清算対象外財産に確実に該当する清算対象外財産を、夫婦財産契約に特記し、その後同財産を分別管理し清算対象財産との混同を予防します。そうすることで、清算対象かそれ以外の財産かという離婚時の争点を回避することができるからです。
また、夫婦財産制として民法上の制度がある以上、法定財産制とは異なる取極めを行うことに加えて、離婚の際の財産分与の清算対象財産の範囲の条件について、夫婦となる者として合意をしたという事実は、離婚の裁判時においても一定程度考慮される可能性が否定できないと考えられるからです。結婚も一つの契約とみなす欧米社会とは異なり、日本では結婚制度に対する公序が強くあるようにも思います。
従って、同居・扶助の義務を否定したり、一方の申出により金銭を支払うことで自由に離婚できたり(東京地判平成15年9月26日平成13(タ)304号・668号においては、定められた金額を払えば申出により自由に離婚ができる条項を無効としています)、財産分与額が不当に低額で著しい不公正な結果になるような夫婦財産契約については、公序という観点から無効になるリスクは否定できません。それでも合理的といえる内容の範囲内で夫婦財産契約を活用するという選択肢の有用性はあるように考えています。
酒井 ひとみ シティユーワ法律事務所
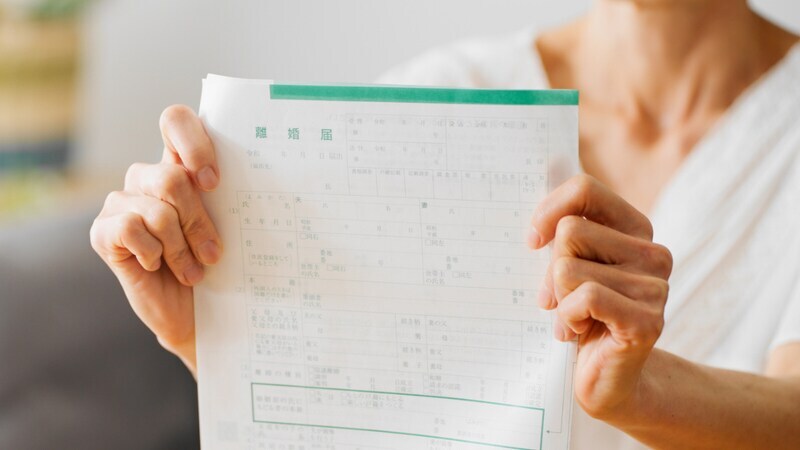


コメント