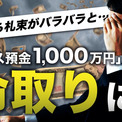
故人が家族のためにと、遺してくれた「タンス預金」。そのお金の存在が、相続をきっかけに家族の誰もが知るところとなり、かえって関係性に亀裂を入れる「トラブルの火種」になるケースも……。本記事では亡き父の「タンス預金」が原因でペナルティを負った山本一家の事例とともに、注意すべき相続税の申告漏れについて、木戸真智子税理士が解説します。※プライバシーのため、実際の事例内容を一部改変しています。
父の多額の「タンス預金」
山本家は、関東圏に住むごく普通の一般家庭。家長である山本氏は、大手企業を定年まで勤め上げ、定年後は夫婦で趣味に勤しむ穏やかな日々を過ごしていました。
ともに暮らす妻とは仲睦まじく、金銭面にも不安を抱えることのない、まさに理想の老後生活。社会人となった子どもたち3人はすでに独立し、それぞれ幸せな家庭を築いていました。年に数回、孫を連れて帰省してくる子どもたちと過ごす一家団らんのひとときが、山本氏にとってなによりの楽しみでもありました。
そんなある日、高齢の家長である山本氏が70代で安らかに亡くなります。
長年ともに連れ添った妻や子どもたちにとって、生前とても穏やかで頼りがいのあった家長との突然の別れは、本当にさみしく辛いものでした。
しかし、そんな悲しみもつかの間。山本家に突然、税務調査が入ることになったのです。税務調査という聞き慣れない状況に戸惑いつつ、調査官からの聞き取りに応じた山本一家。節約家で、きっちりとした性格だった父が遺したいくらかの財産は、父の死後、子どもたちがしっかりと相続税の申告手続きを済ませたはずでした。
しかし調査は想定外の結果となりました。調査官が父の書斎の引き出しを強く引っ張ると、隙間から札束がバラバラと落ちてきました。一家の大黒柱として家計を支えていた山本氏は、なんと独身時代から数十年にわたり、妻や子どもたちがあずかり知らぬ多額の「タンス預金」を貯蓄していたことが発覚したのです。
若いころから堅実だった山本氏が、長年人知れずコツコツと貯めていたその預金は、合計1,000万円ほど。申告漏れ分の追徴税額約160万円に、遺された妻と子どもたちは思わず言葉を失うほかありませんでした。
追徴課税160万円は誰が払う?
山本家に届いたのは約160万円の追徴課税の通知書。その一枚の紙が、穏やかだった家族の関係を静かに壊し始めました。
「この160万円、どうするんだ?」
口火を切ったのは、長男でした。彼は世帯年収700万円、住宅ローンと2人の子どもの教育費に追われ、日々の生活に余裕はありません。
「父さんの遺産から払うのが筋でしょう」とほかの兄弟がいうと、長男の不満が堰を切ったように溢れ出します。
「そもそも、一番そばにいた母さんが気づかなかったなんておかしいじゃないか! それに父さんは、俺たちが家の頭金で苦しんでいたときも、1,000万円も隠して助けてくれなかったんだぞ! あのとき少しでも援助があれば、どれだけ楽になったか……」
その言葉をきっかけに、互いへの不信感が生まれます。「兄さんこそ、父さんから援助してもらったお金を隠してるんじゃないか?」「あなただってもらっていたでしょう」。かつては笑い声が響いた実家は、疑惑と詰問が渦巻く場に変わってしまいました。
資産の申告漏れ…「現金手渡しならバレない」?
銀行などにお金を預けるのではなく、自宅などにまとまった現金を保管しておくことを「タンス預金」といいます。
実は数年前にも、子どもたちに多額の現金を数回贈与していた山本氏は、「現金の手渡しであれば税務署にばれない」 と信じていたようです。山本氏の思惑では、このタンス預金もまた、「生前贈与」として適切に申告することなく、子どもたちに分配するつもりだったのかもしれません。
しかし、税務署は国税総合管理システム(KSK)という専用のシステムによって、過去10年分の収入や通帳等の財産を把握することが可能です。国税庁と税務署は、給与や確定申告のデータが登録された納税者情報を管理しており、そこに記録されている所得状況と預金状況のデータを照らし合わせ、不透明な預金の使い道を調査します。
また、税務署は本人の承諾なしに預金口座を調査することが可能です。この調査は、対象者本人の家族の口座も調査対象になることもあります。山本氏の子どもたちは、数年前に父親から受け取った現金を、それぞれの銀行口座に預金していました。
このように、蓄積された膨大な過去データを照らし合わせることで、税金の申告漏れは高確率で発覚します。特に、相続税の税務調査は他の税目と比べ調査が入る確率が高く、申告漏れの発覚率も高いことで知られています。
申告漏れが発覚すると、後に支払う税金にペナルティが課されるうえ、その記録も残ってしまうため、資産の申告漏れ・隠ぺいは絶対に避けるべきです。意図的な無申告等の悪質なケースと判断された場合、重加算税という最も重いペナルティを課されてしまうこともあります。
残されたのはお金か、それとも不信感か
結局、追徴課税は遺産から支払われましたが、一度生まれてしまった家族への不信感は、簡単には消えませんでした。父がよかれと思って秘密にしてきた1,000万円は、資産ではなく、家族の絆を静かに壊す“毒”となってしまったのです。
では、この悲劇を避けるために、本当に必要だったのはどんなことだったのでしょうか。
問題の本質は、「タンス預金」という行為そのものではありません(むしろ、災害時や相続の際には口座凍結という事態もありえるため、緊急時に備えた蓄えとして10万円~30万円ほどの金額を手元に置いておくことを推奨します)。それが「家族に秘密にされていた」こと、そして「故人の意思が不明瞭だった」ことにあるでしょう。
もし生前に、山本氏が家族に資産の状況を話し合い、遺言書などで「このお金はこう使ってほしい」という意思を明確に示していれば、遺された家族が疑心暗鬼に陥ることはなかったかもしれません。
お金の話は、タブー視されがちです。しかし、家族が元気なうちにこそ資産について話し合い、意思を共有しておくこと。それが、遺された家族を未来の争いから守る、なによりの“相続対策”といえるでしょう。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
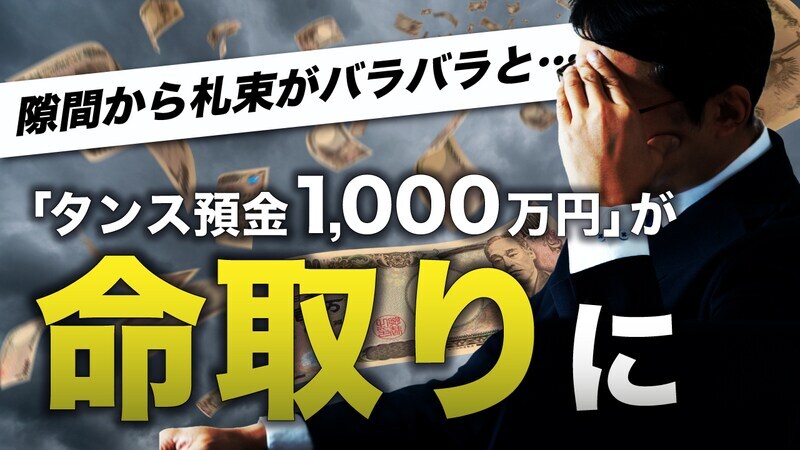


コメント