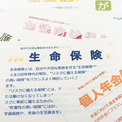
日本人は「保険好き」が多いのですが、保険商品の種類、性質、狙える効果をすべて理解・把握している人ばかりではありません。なかには必要のない保険に延々とお金を払い続ける、当てにしていた保険金が支払われずに慌てるといった事態は、やはり商品への理解不足によるものだといえます。FPが、保険の商品性のキホンから解説します。
保険は「3つの観点」から商品性を考える
保険は、下記の3つの観点で商品性を考える必要があります。
「万が一に備えたい」 → 本来の保障としての位置づけの保険
「確実に貯めたい」 → 貯蓄性のある保険
「効率よく増やしたい」 → 投資性のある保険
当然ながら、保険は万が一のときの「保障」を得ることが目的ですから、保障は当たり前のものとして存在します。

万が一のときの保障という機能だけを持つ保険が、収入保障保険や定期保険です。安い掛金で大きな保障を得るという保険本来の基本形で、掛け捨てです。
そのほかに、貯蓄性のある保険があります。学資保険や養老保険や終身保険です。死亡保障という保険の部分があるため、掛金全額が貯蓄にまわっているわけではないと考えることができます。つまり、保障がある分だけ貯まりにくいということです。
さらに、投資性のある保険も存在します。外貨保険や変額保険です。投資性のある保険も同様で、保障がある分だけ増えにくいといえます。さらに手数料が高いという特徴もあります。商品性の異なるものを混ぜることでわかりにくく、手数料も高くなっているのです。わざとわかりにくくして売っているのではないかと思ってしまうくらいです。
金融庁の「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果等について(2023事務年度)」では、投資性のある保険である外貨建て一時払い保険の短期解約の問題を取り上げて、以下のような指摘をしています。
●約6割が契約後4年間で解約され、契約継続期間の平均は2.5年という非常に短期間となっている
●解約されたものは、継続期間5年以上の同保険と比べて運用成績が大きく劣後している
●初年度の手数料が極端に高い例があり、それに伴う短期間での販売勧誘が背景にあって短期解約につながっている
保険を2.5年という短期間で解約するのが当たり前になっていること自体が驚きですが、その理由が手数料目当ての可能性があることは、さらに驚きです。投資商品における手数料目当ての高コスト商品への誘導という問題と同様に(『【直球】お勧め金融商品を教えてください!…金融機関窓口の「無防備すぎる顧客」に「冷や汗が止まらない」とFPが震えるワケ』参照)、保険商品でも手数料目当ての販売勧誘がされているのです。
契約初期の手数料が極端に高い例も指摘されています。あるとき、どうしてもお金が必要となって解約したくなった場合、当初目的としていた「貯める」「増やす」という目的を達せずにマイナスで戻ってくることになってしまうことも往々にしてあるということです。
人生は思い通りにいきませんから、意図せず途中解約しなければならないこともあるでしょう。契約初期の手数料が高い保険商品よりも、臨機応変に計画変更に対応できる商品の方が、貯蓄や投資には合っています。
金融商品は「目的別」に使い分ける
保険商品ですべてを賄おうとはせず、目的によって分けて考えれば簡単です。
●保障を得たいなら、掛け捨ての収入保障保険や定期保険
●貯蓄をしたいなら、定期預金や個人向け国債
●投資をしたいなら、NISAなどの税制優遇制度を活用して投資
これでいいのです。ライフプランが変更になったときの変更にも対応がしやすいです。
改めて順番に考えていきましょう。
まず、手元の貯蓄が少なく、万が一のことがあったときに家族が路頭に迷うような状態であれば、貯蓄や投資にお金をまわすよりも前に保障を確保することを考えることが大切です。その際には、できる限り安い掛金で高い保障を得ることが重要です。掛け捨ての収入保障保険などが候補になるでしょう。
これは、お金の置き場の話ではなく、万が一のために備えるための保障が必要という話です。保険は保障を得るための道具です。貯蓄や投資のために保険を使う必要はありません。
そして、数年先に使うことが決まっているお金は元本確保型の貯蓄商品を利用して貯めていきましょう。定期預金や個人向け国債です。
そして、将来に向けたお金は、NISAやiDeCoなどの税制優遇制度を活用しつつ、投資をするということです。
投資について少し補足しておきます。将来に向けたお金をすべて投資商品に振り向ければいいということではありません。値下がりする可能性のある投資商品と元本確保型の貯蓄商品を、どの割合で持つかは非常に大切であり難しいテーマです。「リスク許容度」という話です。
定性的には、リスク許容度が高い人(値動きに耐えやすい人)は、
●年齢が低い人
●資産のある人
●投資経験のある人
などと一般的に言われます。このような人たちは投資商品を多めに持ってもいいという考え方です。また、リスク許容度を定量的に計算で求めていく方法も提案されています。定性的な考え方も定量的な考え方も共感できますし、理にかなっています。
しかし筆者は、人それぞれが持つ感情が非常に大切だと考えます。損失に直面すると心穏やかでいられなくなる人は少なくなく、論理的な思考ができなくなって感情に任せて行動してしまい、結果的に失敗して投資から離れていく人もいるのです。
人それぞれの「リスク許容度」を判断するのは容易ではありません。これから投資を始める人は、一気に投資商品の割合を増やさず、少しずつ積み上げていくといいでしょう。下落は必ず来ますので、そのときの自分の感情と向き合いながら、自分が耐えられる下落幅を確認しつつ、投資商品の割合を決めていくといいと思います。
筆者の経験では、自分のリスク許容度がわかるまでには10年以上かかる気がします。よくわからない人は、世間で一般的にいわれる「余裕資金のうち、(100-年齢)〈%〉を投資にまわす」という考え方を参考にするところからスタートしてもいいかもしれません。
小林 篤典 FP事務所 きずな 所長
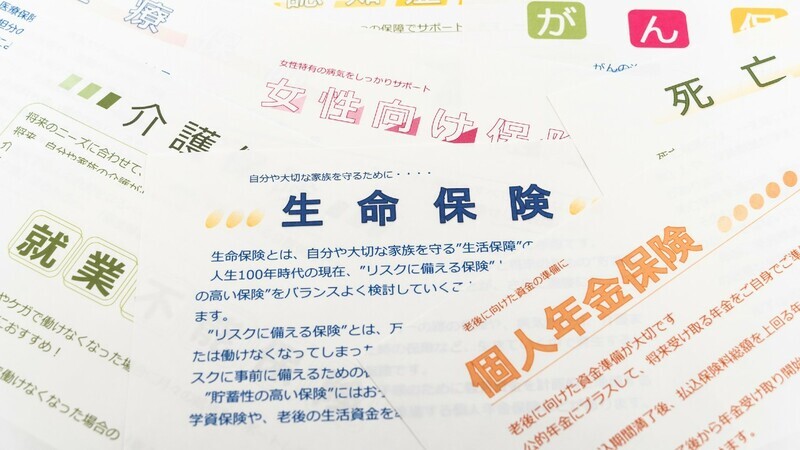


コメント