
「銀行に入れば一生安泰」――かつての黄金神話は今や幻想となっています。大手銀行の支店長として年収1,600万円を誇った関口智一さん(仮名・54歳)は、55歳の役職定年を目前に「キャリアデザイン研修」への参加を命じられました。表向きは「これからの人生設計のため」とされるこの研修、実態は「あなたの居場所はもうない」という銀行からのメッセージです。同期入社100人のうち役員の階段を上れるのはわずか3人。残りの97人は55歳で役職を外され、年収は一気に3割減。60歳の定年後はさらに減少します。この現実は銀行員だけでなく、多くの大企業サラリーマンが直面する「静かな危機」なのです。この危機を乗り越え希望ある老後を描く秘策を、FPの青山創星氏が詳しく説明します。
誇り高きメガバンカー、突然の「研修」通知に震える
「関口さん、来月のキャリアデザイン研修、出席よろしくお願いします」
人事部からのその一通のメールが、関口さんの人生を変えました。メガバンクの支店長として年収1,600万円、部下50人を率いる立場にあった関口さんは、54歳という年齢に差し掛かったばかりでした。
表向きには「50代からのキャリア構築を考える研修」とされるこの「キャリアデザイン研修」。しかし、銀行員なら誰もが知る、その本当の意味は「あなたはもう役員コースではない」という烙印だったのです。
同期入社は100人。新入社員時代、彼らは「銀行マンになれば一生安泰」と胸を張っていました。実際、30代で年収1,000万円を突破し、40代で支店長になり、家族を養い、マイホームを購入し、子どもを私立大学に通わせることもできました。
そんな順風満帆の人生を歩んできた関口さんでしたが、研修の内容は残酷なものでした。
「役職定年」の残酷な現実…年収3割減は序章に過ぎない
「皆さん、銀行での輝かしいキャリアお疲れ様でした。これからは第二の人生を考える時期です」
研修講師のその言葉に、会場の空気が凍りついたのを感じました。参加者は全員50代前半の管理職。つい先日まで「今期の目標必達」「部下の育成」に躍起になっていた面々です。
研修の本題は容赦ありませんでした。55歳での役職定年後、ほとんどの場合、銀行関係会社か取引先企業への出向となり年収は3~5割減。そして転籍、再雇用後60歳時点ではさらに大幅に減少します。つまり、関口さんの場合、現在の1,600万円から55歳では1,000万円(4割減)に。また、60歳では600万円を大きく下回る見込みです。
同期100人のうち、役員候補として残れたのはわずか3人だけ。関口さんを含む残りの97人は役職定年により、管理職の座から降りることになりました。
「住宅ローンがまだ残っています。子どもは大学生で、親の介護も始まっているんですが……」
隣の席の同期が呟いた言葉が胸に刺さりました。彼だけではありません。参加者のほとんどが多かれ少なかれ似たような状況だったのです。
最も衝撃的だったのは、銀行関連会社への転籍組の話です。40代半ばで銀行本体から関連会社へ出向した同期は、すでに年収が800万円程度に下がっていました。彼らは「早めに出向した方が良かった」と言います。なぜなら、50代で突然の年収ダウンよりも、40代から徐々に下がる方が生活設計を立て直しやすいからです。
「銀行だけじゃない」大企業で広がる役職定年制度の波紋
「役職定年」は銀行特有の制度ではありません。人事院の「令和5年民間企業の勤務条件制度等調査」によれば、役職定年制度を導入している企業の割合は全体で20.8%となっています。特に従業員数が多い企業ほど導入率が高く、従業員500人以上の企業では38.7%に達しています。
この調査では、役職定年制度を設けている企業における役職定年年齢も明らかになっています。部長級の役職定年年齢は「55歳」が33.5%と最も多く、次いで「60歳」が19.6%、「57歳」が19.3%となっています。課長級では「55歳」が40.3%と最も多く、「60歳」が19.2%と続いています。つまり、多くの企業では55歳前後で役職から外れる傾向があるのです。
役職定年制度は、企業にとって人件費削減と若手登用の両立を図る手段として機能しています。しかし、当事者にとっては突然の収入減少という厳しい現実をもたらします。
60歳以降の「第三の人生」…年収半減の衝撃と資産形成の重要性
60歳の定年後、多くの企業では再雇用制度を利用して65歳まで働くことができます。しかし、その待遇は厳しいものです。
日経BPが2021年1月に40~74歳を対象に実施した「定年後の就労に関する意識調査」(約2,400人対象)によれば、定年後再雇用では勤務時間や日数は63.5%が「定年前と同水準」と回答している一方、年収については「定年前の6割程度」が20.2%と最も多く、「5割程度」が19.6%、「4割程度」が13.6%と続いています。つまり、働く量はほとんど変わらないのに、給与が4~6割減となるケースが過半数を占めているのです。
「でも年金があるから大丈夫では?」と思われるかもしれません。しかし、厚生年金の満額受給は65歳から。60~65歳は「年金空白期間」となります。また、厚生労働省の統計によれば、令和5年度の厚生年金の平均受給額は月額15万円程度。これに国民年金を合わせても、現役時代の生活水準を維持するには不十分です。
「WPP戦略」で描く、希望ある老後設計
このような収入減少の現実に対して、注目されているのが慶応義塾大学の権丈善一教授や名古屋経済大学の谷内陽一教授が提唱している「WPP」という考え方です。
WPPとは、「Work longer(長く働く)」「Private pensions(私的年金)」「Public pensions(公的年金)」の頭文字をとったもので、人生100年時代の新しい年金受給戦略です。WPPの基本的な考え方は野球の「継投」に例えられます。
まず「Work longer」が先発投手として65歳頃まで働き、「Private pensions」が中継ぎ投手として就労引退から公的年金受給開始までをつなぎ、最後に「Public pensions」が抑え投手として終身給付で人生を締めくくります。
具体的には、50歳頃から自分の会社の役職定年年齢と再雇用条件を確認し、60歳以降もできるだけ長く働ける準備を整えます。同時に、iDeCoやつみたてNISA、退職金の運用といった私的年金の準備を加速させます。そして65歳から70歳または75歳まで公的年金の受給を繰り下げることで、年金額を最大84%まで増額させるのです。
例えば関口さんの場合、55歳で役職定年を迎えた後、関係会社で65歳まで働き、その後退職金と資産運用で70歳9ヵ月まで生活し、70歳9ヵ月から増額された公的年金を受け取ることで、安定した老後を実現できます(図表2のWPP型)。この戦略では、準備する自己資金が少なくて済むのと想定寿命を超えた場合でも、生涯安定した収入を確保できる点が大きな強みです。


役職定年時代を乗り越える6つの重要ポイント
役職定年や再雇用による収入減少は、もはや避けて通れない現実です。しかし、適切な準備と前向きな取り組みによって、この変化を「新しい人生のスタート」に変えることができます。
1. 早期の現実把握と計画立案 40代後半から自分の会社の制度を詳しく調べ、収入減少のタイミングと幅を把握しましょう。
2. WPP戦略の実践 「長く働く」「私的年金の充実」「公的年金の繰下げ受給」の三つの柱を組み合わせ、自分に最適な老後設計を描きましょう。
3. 税制優遇制度の最大活用 iDeCoやつみたてNISAといった制度を早期から活用し、退職金の運用方法も事前に検討しておくことが重要です。
4. 健康とスキルの維持 長く働くためには、健康管理と継続的な学習が不可欠です。新しい技術やスキルを身につけ、価値ある人材であり続けましょう。
5. 多様な働き方への対応 柔軟な働き方を受け入れることで、より長く社会に貢献できます。
6. 専門家への相談 夫婦の年齢差にもよりますが、夫婦の厚生年金、国民年金の受給時期をずらすことによって加給年金や振替加算を受け取りながら年金の受給額を増やせる場合もあります。また、実際には税金や社会保険料の影響も勘案する必要があります。この分野に強い社会保険労務士やファイナンシャル・プランナーなどに相談するとよいでしょう。
人生100年時代の到来は、確かに従来の人生設計を大きく変えました。しかし、それは同時に「より充実した長い人生」を送るチャンスでもあります。役職定年は終わりではなく、新しい人生ステージの始まりなのです。適切な準備と前向きな姿勢で、この変化を自分の人生を豊かにする機会に変えていきましょう。
参考:人事院「民間企業の勤務条件制度等調査(令和5年) 」 https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/toukei/0111_kinmujouken/0111_ichiranr05.htmlファイナンシャルプランナー 青山創星
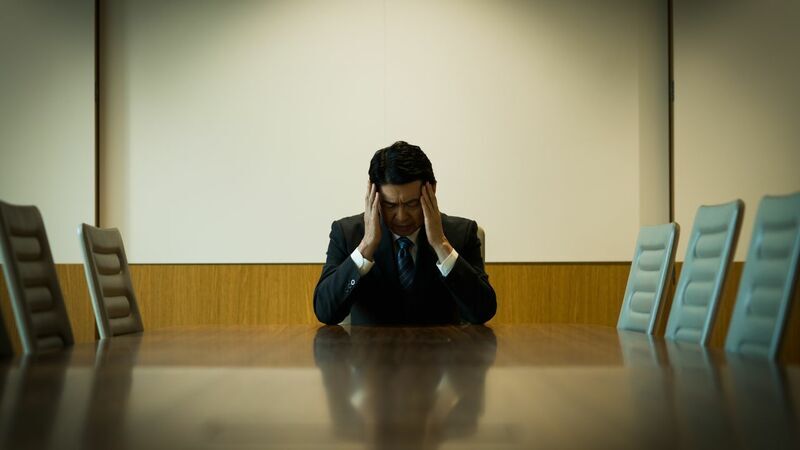


コメント