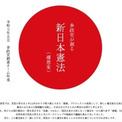
今回の参議院選挙では、参政党をめぐる話題が尽きない。中でも法律関係者のあいだで強い懸念を呼んでいるのが、同党が2025年5月に作成した憲法改正案とみられる「新日本憲法(構想案)」だ。
この案では、現在憲法が保障してきた多くの国民の権利が明記されておらず、あとで「知らなかった」では済まされないほどの内容となっている。
すべてを取り上げるにはあまりに論点が多いため、この記事では、国民の生活に直結する3つの問題点に絞って、憲法問題に関する訴訟に数多く関わってきた平裕介弁護士に解説してもらった。
<編中:隅付き括弧は脚注番号。出典・説明は記事末尾に掲載している>
●日本経済が衰退、手取り減少、さらなる生活苦のおそれ実に多くの問題をはらむ構想案なので、そもそも、国民の生活に直結する3つの問題に絞るということ自体、本来無理です【1】。
ただ、あえて3つに限定するなら、もし成立・施行されることになれば、まずは日本の経済が衰退し、個々人の収入の手取りが減り、さらに生活が苦しくなるおそれがある、ということが考えられます。
参政党案第19条第2項が「土地は公共の財産」であると規定していることや、「財産権」(現行憲法第29条第1項)を保障する明確な規定もないので、現行憲法のもとで保障されている「私有財産制」【2】を否定するように読めます。少なくともこの点はあいまいで不明確です。
外国人だけではなく、日本国民の土地という重要な財産についても、私有財産制が保障されないと考えられる以上、たとえば、財産の利用や処分を強く制限する経済統制に関する法律や、恣意的な資産の再配分を可能とする法律などが作られても、違憲性を問いにくいという事態に陥ります。
このようなことから、国民の日常的な経済活動に大きな不安をもたらすことになります。
たとえば、土地や家屋など、自分の資産に対する安心感が損なわれると、長期的な投資や消費を控える心理が生まれます。
また、企業や投資家なども、私有財産制度や財産権が十分に守られないような国では、その活動が萎縮してしまい、経済成長にブレーキがかかるおそれがあります。
ですから、現行憲法下の私有財産制を基礎とする市場経済の信頼が揺らぎ、その結果、日本の経済が衰退し、個々人の収入の手取りが減り、国民の生活が今以上に苦しくなるおそれがある、ということをまず指摘せざるをえません。
●自分の気持ちや考えをアップできなくなるおそれ今日、SNSを"見るだけ"の人も含めると、SNSをやらないという人はほとんどいないでしょうから、SNSはほぼすべての世代にとって、私たちの生活に身近なものになったと思います。
しかし、参政党案を前提とすると、国民がSNSやブログ、メディアの媒体などで、気軽に自分の意見を発信できなくなる危険が生じることが考えられます。
参政党案第8条には「国民」の基本的な自由と(「権利」ならぬ)「権理」が規定されていますが、参政党案第5条で、その「国民」の「要件」について「日本を大切にする心を有することを基準として、法律で定める」という規定を置いています。
この「日本を大切にする心」については、参政党案の本文には一切説明がないものの、「注」として「規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである」という解釈(法解釈)に係る説明が付記されています。
しかし、「日本を大切にする心」にせよ、「我が国に対する害意がない」にせよ、非常に抽象性の高い言葉ですから、この要件の認定について権力者が濫用的な運用をする危険が大きいというほかありません。
たとえば、今、こうしてメディア媒体を通じて公表しているこの記事自体も、特に参政党が政権与党側になれば、時の政府に批判的な表現をおこなっている者が「日本を大切にする心」がないとか、「我が国に対する害意がない」とはいえない者である、などと恣意的に認定されてしまう原因になりえます。
そして、そのような認定をされると、もはや「国民」ではないということになりますから、仮に、ただちに日本国籍を剥奪されないとしても、そのような者には「国民」の「自由」も「権理」も認めない、あるいは権利を強く制限できる、という運用をされることになりかねません【3】。
「日本を大切にする心」を有しないと認定された「国民」については、その「自由」も「権理」も、「日本を大切にする心」を有すると認定された者と同程度には保障されない、などということになれば、不当に個人の基本的人権が制限され、あるいは奪われ、国家権力による弾圧を受けることは容易に想定できます。
ですから、参政党案の憲法が成立・施行された場合には、SNSなどで気軽に自分の気持ちや考えをアップできなくなってしまうでしょう。
とりわけ、このような記事は事実上書けなくなります。
ちなみに、参政党案第8条第3項では、「自由」には「責任」が伴うとされ、「権理」には「義務」が伴うと明記され、同時に「公共の福祉」(現行憲法第12条、第13条など)ではなく「公共の利益」・「公益」が強調されています(参政党案第8条)。
これは、「自由及び権利には責任及び義務が伴う」ことを規定し、「公益及び公の秩序」を強調する自民党の憲法改正草案12条と似ており、要するに、現行憲法のもとで認められている基本的人権をより広く制限できるようにする規定といえます【4】。
このこと自体にも大きな問題があるわけですが、こうした「自由」や「権理」すら「日本を大切にする心」があると権力者によって認定されなければ、制限されたり剝奪されたりしてしまうおそれがあるわけで、これは本当に恐ろしいことだと思います。
●不当な逮捕、拘束、拷問、国外追放のおそれ特に選挙期間になると、政治家が街頭演説をしている公共のスペースの場で、A4からA3サイズくらいの大きさ用紙に時の政府の政策などに批判的なメッセージを書いたものを持参し、政治家に対して抗議をしたり、あるいは黙って平穏に抗議をしたりしている人もいます。
しかし、このように黙って平穏に抗議をしている人であっても、参政党案第5条等に照らすと、「日本を大切にする心」がないとか、「我が国に対する害意がない」とはいえない、などと認定され、令状なく逮捕され、長期間拘束され、拷問【5】を受け、残虐な刑罰【6】を受けるなどのおそれがあると言わざるをえません。
現行憲法に明文で存在する令状なく逮捕されない権利の規定(33条)も、公務員による拷問や残虐な刑罰を絶対的に禁止する規定(36条)も、参政党案には明文規定がありません。
そのうえ、以上のとおり「国民」の要件を欠くと認定されてしまえば「自由」や「権理」ですらより制限されたり剝奪されたりするわけですから、突然逮捕され、長い間身体を拘束され、拷問を受け、しまいには残虐な刑罰を受けたり、あるいは「国民」ではないとなれば在留権も否定されたりするでしょうから、一方的に国外追放されるおそれもがあると指摘せざるをえないわけです。
私は現在、「角川人質司法違憲訴訟」という憲法訴訟・公共訴訟の原告代理人を担当しています【7】が、「人質司法」は決して他人事ではありません【8】。
そして、現行憲法のもとですら、罪を否認したり黙秘しているというだけで、自らの身体を人質にとられて事実上自白を強いられ、過酷で劣悪な場所に長期間拘束されることになるのが現実ですから、仮に参政党案の憲法に変わってしまうと、今以上に厳しい人権侵害が起こるであろうことはほとんど明らかでしょう。
「何だか大げさなことを言うなぁ」などと感じる人もいらっしゃるでしょうが、参政党案を憲法学・法学の観点から客観的に分析し、想定される危険やリスクを普通に指摘すれば、以上のようなことを言わざるをえません。
ですから、まったくもって大げさな評価でも、オーバーな表現でもありませんし、読者の方々の不安を煽る意図なども一切ありません。
●「当たり前のことが書いていない」こと自体リスク参政党案には国民主権の明文規定がないわけですが、「基本的人権」(現行憲法第11条)という文言や、以上に述べた国民の個々の人権が個別に規定されていないことなどについて、「当たり前のことだから書いていないだけだ」などという反論がありえます。
しかし、「当たり前のことだから書いていない」というのは、1つの解釈(法解釈)にすぎず、そのような解釈は変更されうるものです。
実際に、第2次安倍内閣は2014年7月、従来の憲法9条の解釈に関する政府見解、すなわち個別的自衛権のみを認め、集団的自衛権は行使できないという解釈を変更し、集団的自衛権行使を一部容認する内容を含む閣議決定をおこないました【9】。
ですから、実際に、国民の権利や自由などに関して重要なことを明文で書いていないことそれ自体が大きなリスクだといえます。
「国民の要件を定めているからといって国籍の剝奪するつもりはない」とか「人権侵害のリスクは特に想定していない」とか「日本を大切にしてほしいという声を反映させたにすぎない」などといった反論【10】も想定されるところですが、同様に、これらも1つの解釈を示したものにすぎず、やはり将来的に規定や文言の解釈が変更されうるという危険性を内在する言い分だと考えておくのが無難でしょう。
ちなみに、参政党案第8条第1項で、国民の「主体的に生きる自由」を規定しており、これが参政党案の「注」によると、「包括的な自由権との解釈である」と説明されています。
しかし、これも同じような話で、この解釈もまた変更されうるものです。
「包括的な自由権」だというのであれば、それを明文で、「注」ではなく本文に明確に書いていないということ自体が大きなリスクだと言わざるをえません【11】。
ですから、参政党案第8条第1項があるから国民のさまざまな基本的人権が保障され、これらが侵害される危険はない、ということにはならないわけです。
●専門家のリーガル・マインドを活用してほしい憲法草案をつくる行為は、世間一般の常識だけで判断可能な範囲を超えているという意味で「難しい」問題を含んでおり、そこには専門的な知見が要求されます。
東京タワーやスカイツリーといった高い建物を建てるのも、大型の発電所を設計して実際に動かすのも、世間一般の常識だけではどうにもならず、関係する専門家の知見が必要です。
これらの行為と同じように、憲法草案をつくるのには、専門家の知見や、あるいはその核心部分ともいえるリーガル・マインドが必要になります。
リーガル・マインドは、「法的な考え方」【12】だとか「法律家にはある程度共有されている感覚のようなもの」【13】「物事の正義や公平の感覚」【14】 などと説明されます【15】。
リーガル・マインドが取り入れられていない憲法あるいは憲法草案だと、以上に述べたような人権侵害が生じないようにするために本来明記されていなければならないような基本的人権の規定が明記されていなかったりするわけです。
近代の立憲的憲法の草案といえるためには、リーガル・マインドを有する専門家の知見を聞いたうえで、それを取り入れることが不可欠です。
専門家の話を鵜呑みにせよとか、言いなりになれということではありません。
とはいえ、憲法草案をつくる際には、最低限、憲法などの法の専門家の意見を広く聞き、近代憲法の要素といえる規定については「当たり前」の規定であっても、しっかりと明記する内容のものをつくることが重要だといえます。
専門的な知見を無視、軽視し、あるいは専門的な知見を有しない人だけで建物や発電所を設計し作ってしまえば、たとえば震度5程度の地震でも、高い建物が傾いて使えなくなったり、発電所が故障したり、あるいは重大な事故を起こしたりするということになってしまうでしょう。
これは憲法草案を作る場合も同じです。
憲法や法学の領域でも、専門的な知見は現代社会の国民生活に不可欠だからです【16】。
現在、リーガル・マインドを有する憲法学者や弁護士を中心に、多くの法律家が参政党案の問題点を多数指摘しています。
この記事はそのごく一部を述べたにすぎません。今後も多くの専門家が意見や記事を公表することが予想されます。
ぜひ専門家の声にも耳を傾けてください。
【1】2012年に公表された自民党の憲法改正草案も、法律家らから、前文を含め、条文ごとに多くの問題点があると批判されています(読みやすい文献として、伊藤真『赤ペンチェック 自民党憲法改正答案』(大月書店、2013年)があります)が、このたびの参政党案は、この自民党の改正草案や、あるいは大日本帝国憲法と同程度に、あるいはそれ以上に、実に多くの問題を含むものと考えられることから、その問題点は10や20では到底利かないものと考えられます。
【2】判例(最大判昭和62年4月22日民集41巻3号408頁)は、現行憲法第29条が「私有財産制度を保障している」と理解しています。なお、憲法学説も、現行憲法29条1項は財産権を保障するとともに私有財産制の保障をするという2つの面を有すると理解しています(芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法 第八版』(岩波書店、2023年)255頁)。
【3】木村草太東京都立大学教授も、参政党案第5条について特に警鐘を鳴らしており、「『日本を大切にしていない』という理由で、一方的に国民から国籍を剝奪し得ることになります」と指摘しています(週刊文春67巻28号(2025年7月24日号)20頁)。
【4】伊藤・前掲『赤ペンチェック 自民党憲法改正答案』37頁参照。なお、基本的人権は、「人間であることにより当然に有するとされる権利」であること(芦部・前掲『憲法 第八版』82頁)から、そもそも、それを行使するときに、何らかの義務を果たす必要はありません。例えば、たとえ納税の義務を果たしていない人であっても、選挙権や表現の自由を行使することはできます。むしろ、義務を負っているのは国家の方であって、国民が権利を行使するときに、国家はそれを保障する義務を負います。これが憲法上の権利と義務の本来的な構造であり、憲法上の権利を行使する国民の側に当然に義務が生じるというわけではありません。ところが、自民党案第12条後段も参政党案第8条第3項前段も、この構造を誤解させるような表現になっています。権利(基本的人権の行使)には義務が伴うなどという表現は、国民の基本的人権を今以上に制限し、権力者によって国民の義務を拡大させたりする根拠に悪用されるおそれがあります(伊藤真『憲法問題』(PHP研究所、2013年)90~91頁参照)。
【5】「拷問」(現行憲法第36条)とは、その実行者が対象者に身体的・精神的に激しい苦痛を与え、対象者を抑圧して、実行者の意のままに動く(典型的には、刑事事件の「自白」をさせる)ようにすることといえます(戸松秀典=今井功編著『論点体系 判例憲法 2』(第一法規、2013年)390頁〔喜田村洋一〕参照)。
【6】「残虐な刑罰」(現行憲法第36条)とは、「不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰」(最大判昭和23年6月23日刑集2巻7号777頁)をいい、例えば、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでによる死刑執行などが「残虐な刑罰に当たります(長谷部恭男編『注釈日本国憲法(3)』(有斐閣、2020年)379頁〔長谷部恭男〕参照)。
【7】https://proof-of-humanity.jp
【8】https://innocenceprojectjapan.org/hostage-justice
【9】このような閣議決定の方法により憲法の規定の解釈を変更することは、「憲法を解釈する権力(憲法解釈権力)」(蟻川恒正『憲法解釈権力』(勁草書房、2020年)3頁)の行使だと考えられます。憲法解釈権力は、「新憲法の制定と実質的には同等の効果をもたらしうる力」を有するものと解説されます(同書5頁)。
【10】週刊文春67巻28号(2025年7月24日号)21頁参照。
【11】包括的な自由権ということが明文で書いていない理由は、明文で書けなかったからだろうと考えられます。「日本を大切にする心」を国民の要件に据えること自体が、例えば、現行憲法第19条が保障する思想良心の自由(内心の自由)を侵害する、あるいはその危険性の高いものといえることから、あえて本文ではなく「注」で書いたものと分析できるでしょう。
【12】大谷實編著『エッセンシャル法学 第8版』(成文堂、2025年)8頁〔大谷實〕。
【13】宍戸常寿=石川博康編著『法学入門』(有斐閣、2021年)14頁〔内海博俊〕。
【14】川﨑政司『新・法律学の基礎技法Ⅰ』(弘文堂、2025年)38頁。
【15】「リーガル・マインド」を詳しく解説した文献として田中成明『法学入門 第3版』(有斐閣、2023年)189〜191頁。
【16】長谷部恭男『法律学の始発駅』(有斐閣、2021年)194~195頁は、「人々の慣行を通じて徐々に実定法が成立していた前近代と違い、近代社会では、何が自分たちの行動を規律する実定法か人々が感覚的に把握できる余地は狭まります。専門的な法律家集団に、何が法かをコストをかけて教えてもらう必要があります。(中略)市民に向けて法の現状を説明し、法の立案・制定とその解釈・適用に与る法律家集団の責務は、それだけ増すことになります。」とします。
【取材協力弁護士】
平 裕介(たいら・ゆうすけ)弁護士
2008年弁護士登録(東京弁護士会)。主な業務は行政訴訟、憲法訴訟。行政法研究者でもあり、多数の論文等を公表。大学やロースクール(法科大学院)で行政法等の授業を担当(非常勤)。審査会の委員や顧問など、自治体の業務も担当する。
事務所名:AND綜合法律事務所
事務所URL:https://and-lawoffice.com/
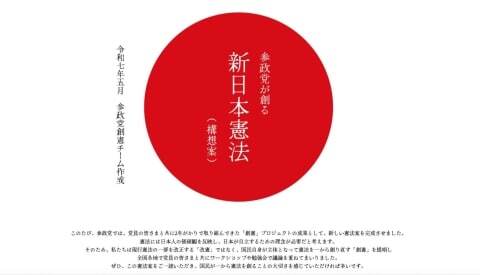


コメント