
金融庁は暗号資産を「金融商品取引法(金商法)」の枠組みとすることを本格検討しています。ここでは、暗号資産への「分離課税導入」「出国税適用拡大」が実現した場合のメリット・デメリットについて、暗号資産に精通する国際弁護士の森和孝氏が具体例を挙げて解説します(5回のうち3回)。
分離課税の影響
1.期待される改善効果
現行制度では最大55%という高税率負担が投資意欲を削ぐ要因となっています。分離課税導入により、所得にかかわらず一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用され、特に高所得者の税負担が大幅に軽減されます。年収2,000万円以上の投資家が1,000万円の暗号資産利益を得た場合、現在の約550万円から約203万円へと約347万円もの大幅な軽減となります。
また、損失繰越控除の不可という問題も解決されます。現行制度では暗号資産取引で発生した損失を翌年以降の利益と相殺できませんが、分離課税導入後は最大3年間損失を繰り越して相殺できるようになります。確定申告の煩雑さも改善され、明確な税制により国内企業のWeb3関連事業への参入が促進され、海外流出していた有望な人材の育成・定着も促進されることが期待されます。
2.相続税110%課税問題と改善の可能性
現行制度で最も深刻な問題が、相続時の重複課税による「110%課税問題」です。相続発生時に時価評価で最大55%の相続税が課され、その後の売却時に被相続人の取得価格を基準とした所得税が課されるため、同じ含み益に対して二重に課税される構造となっています。
具体例として、2015年に500万円で購入されたビットコイン(約166.67BTC)が本日の史上最高値112,000ドルで評価すると約26.7億円の価値となった場合を考えてみましょう。
a.現行制度での税負担
●相続税:約14.7億円(相続財産の55%)
●売却時所得税・住民税:約14.6億円(譲渡益26.65億円の55%)
●総税額:約29.3億円(相続財産の約110%)
今回の税制改正により分離課税(20.315%)が導入されれば、売却時の税負担が大幅に軽減され、110%課税問題は相当程度改善される可能性があります。
b.改正後の税負担(予想)
●相続税:約14.7億円(変更なし)
●売却時所得税・住民税:約5.4億円(譲渡益26.65億円の20.315%)
●総税額:約20.1億円(相続財産の約75%)
c.取得費加算特例適用時の更なる軽減可能性
もし取得費加算特例が暗号資産の相続にも適用されるのであれば、相続開始から3年10ヶ月以内に譲渡するという条件を満たすことで、税負担をさらに大幅に軽減できる可能性があります。
この特例では、支払った相続税の一部を取得費に加算できるため、同じ例で計算すると、下記のようになります。
●加算可能な相続税:約14.7億円
●修正後の取得費:500万円 + 14.7億円 = 約14.75億円
●修正後の譲渡所得:26.7億円 - 14.75億円 = 約11.95億円
●所得税・住民税:約2.4億円(11.95億円の20.315%)
●総税額:約17.1億円(相続財産の約64%)
この場合、重複課税の問題は実質的に大幅改善されることになります。ただし、この特例が暗号資産にも適用されるかは現時点では不明確であり、金商法適用後の制度設計における特例の適用範囲の明確化が重要な課題となります。
3.注意すべきリスクと考慮事項
一方で、専門家からは分離課税導入にも注意すべき点があると指摘されています。
●低所得者層への影響については、ケースによっては負担増となる可能性があります。現行制度では年収300万円で暗号資産利益100万円の場合、約15%の課税となりますが、これが固定20.315%になる場合は負担が増加します。
●出国税の適用拡大は極めて重大な懸念です。暗号資産が金融商品に位置づけられることで、株式のように国外移住時の含み益に15%の出国税が課されるリスクがあります。現在は対象外の暗号資産が新たに課税対象となる可能性があり、大口保有者には重大な影響を与えます。この点について次章で詳しく検討します。
●将来的な税率変更の可能性も考慮すべき要素です。他の金融所得同様、将来的に税率が変更される可能性もあり、長期的な税負担については不確実性があります。
●分離課税適用範囲の限定: 最も重要な課題として、海外取引所での取引利益や、日本の取引所で上場していない暗号資産銘柄については、分離課税の適用範囲から除外される可能性があります。筆者の予想では、これらは適用範囲外となる可能性が高く、除外されれば現行の総合課税(最大55%)のままとなります。これは投資家の選択肢を大幅に制限する重大な問題です。例えば、国内取引所で取り扱われていない有望な暗号資産への投資や、より有利な条件を求めて海外取引所を利用する投資家にとっては、分離課税の恩恵を受けられない可能性があります。結果として、国内の限られた銘柄のみが優遇され、投資の多様性や機会の平等性が損なわれるリスクがあります。
4.制度改正の全体的評価
今回の分離課税導入は、長年業界から要望されてきた制度改正であり、基本的には投資環境の改善に寄与する歓迎すべき変更です。特に高税率に悩まされてきた投資家にとっては大幅な負担軽減となり、損失繰越制度の導入と合わせて、より公平で合理的な税制となります。
ただし、個人の所得状況や投資スタイルによっては、必ずしもすべてのケースで減税効果を享受できるわけではないため、自身の状況に応じた影響の評価が重要となります。
出国税適用拡大の重大な影響
1.現在の状況と今後の変化
現在、暗号資産は出国税の対象外となっており、1億円以上の資産を保有する投資家が海外に移住する際にも、暗号資産の含み益に対して課税されることはありません。このため、多くの暗号資産長者がドバイやシンガポールなどの税制優遇国に移住し、そこで暗号資産を売却して無税で利益確定するという戦略を取ってきました。
しかし、金商法適用により暗号資産が有価証券扱いになれば、出国税の対象となる可能性が高く、1億円以上の含み益を持つ投資家は海外移住時に約15%の出国税が課されることになります。
具体的な影響例
26.7億円の暗号資産(取得価格500万円)を保有する投資家がドバイに移住する場合
●現行制度:出国時の課税なし、ドバイやシンガポールに移住後に利確すれば無税
●改正後:出国時に約4.0億円の出国税(含み益26.65億円の15%)
この変更により、従来の海外移住による税負担回避戦略は実質的に封じられることになります。
2.2027年施行前の駆け込み移住の可能性
制度改正の施行が2027年に予定される中、暗号資産長者の間では制度変更前の駆け込み移住が増加する可能性があります。特に以下のような動きが予想されます。
制度確定から施行までの期間に、大口保有者による海外移住が集中的に発生する可能性があります。
移住先の多様化
ドバイやシンガポールなど、暗号資産の利益に非課税の国や地域への移住が加速する可能性があります。特にビットコインなどの暗号資産で不動産を購入でき、ゴールデンビザが容易に取得できるドバイへの移住が増加することが見込まれます。
3.移住タイミングの重要性
出国税は海外移住時の含み益に対して課税されるため、移住のタイミングが極めて重要になります。ビットコインが史上最高値を更新するような状況では、移住の遅れが多額の税負担増加につながる可能性があります。
ただし、移住には居住実態の証明、国際的な租税条約の適用など、複雑な事情の検討が必要であり、専門家による綿密な計画立案が不可欠です。また、形式的な移住だけでは税務当局に非居住者と認められない可能性が高く、実質的な生活拠点の移転が求められます。
※ 次回記事では、トークン発行に伴う厳しい規制、事業者への負担の増大について解説します。
森 和孝 Eminence Luxe(ドバイ不動産仲介会社)Founder/CEO One Asia Lawyers 国際弁護士(UAE法、シンガポール外国法、日本法)
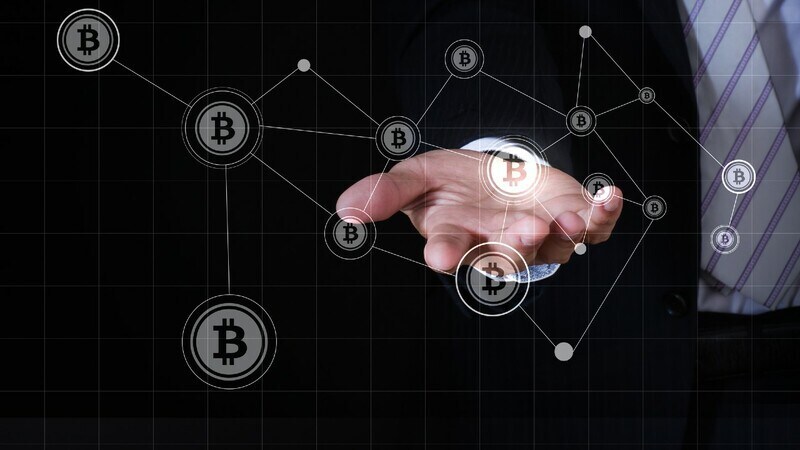


コメント