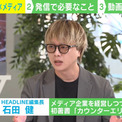

参院選の結果を受け、石破総理の退陣論など様々な動きがあるが、その結果にメディアはどう影響したのか。ニュース番組『ABEMAヒルズ』のコメンテーターでThe HEADLINE編集長の石田健氏と考える。
【映像】日本維新の会 吉本代表のXに投稿された“コント動画”
今回の選挙を通じて、選挙報道とメディアについて感じたことを石田氏は次のように語る。
「2024年の選挙で、いわゆるソーシャルメディア対オールドメディアの対立軸が非常に意識されたので、各局ともに選挙の当日よりも前に様々な特集をしていた印象はある。従来であれば、『中立公正でやってください』という放送法などの要請を受けて、メディア側が過度にそれを意識しすぎてしまう、あるいはそういった法律に忖度してしまうことで、ただ公約を並べて『こういう意見があります。以上です』というような形だった。そこから、深い話をしっかりと時間をかけてやってほしいというニーズに対して、少しずつ大手のメディアも応え始めたという意味では、ポジティブな変化だと思う」(石田氏)
各党の戦略や発信はどのように感じたか。
「ネットの影響力が無視できないことは多くの有権者、候補者も分かっている。国民や参政党、もともとネット地盤が強い層に関しては積極的に活用していたし、維新の動画のように、ネット戦略をより強化しようという動きを見せたものの、あまり票には繋がらなかった党もある。ネットと地盤、それから争点設定をどう組み合わせるかが今後の焦点になってくる」
メディアの運営者でもある石田氏。発信の際に考えていることを明かした。
「基本的に報道機関が果たす役割は非常に大きい。今回の国政選挙のように、全国に候補者がいて、様々なプロフィール・主張があって、それを整理して届ける体力があるのは報道機関であることは間違いない。ただその上で、報道機関が十分にできていない領域でいうと、『なぜ参政党が今こんなに注目を集めているのか』『参政党は何を語っていて、それが有権者にどう刺さっているのか』というストーリーを解釈して客観的に届けるところだ。そういったところを届けられるように意識していた」
選挙を通じて話題になったのは動画での発信が多かったが、テキストと動画の影響力は。
「選挙に限らず、今は動画の時代になってしまった。テキストの良さは、リンクを貼ることでファクトチェックや引用元を明示できること。その意味で、テキストの価値はまだ減じていかない。ただ、例えば政治であれば、政治家のテンションや温度感、言葉遣いなど、動画のほうが情報量が多く、それを見たいという有権者が多い。我々のようにそういった情報を届ける際も、動画の存在を無視できない」
今後の報道はどのようになっていくか。
「おそらく5年ぐらいすると、どこの報道機関が出しているというよりも、誰が喋っているのかが重要視される。そうなったときに、正確な情報をコストをかけて届けている、というメディア側の主張は、あまり届かなくなってくる。フェイクニュースも含めて、政治家が語ってくるナラティブを報道側が超えられるか、報道側がそこの土台に乗れるかが大事なので5年、10年かけてメディア側も投資していかなくちゃいけない領域だと思う」
(『ABEMAヒルズ』より)
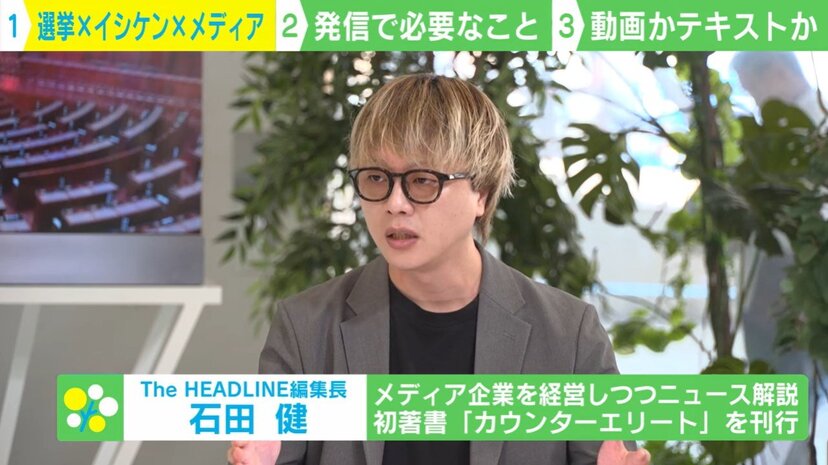


コメント