
バブル期の不動産投機抑制を目的に導入された地価税は、1997年以降、課税が停止されたまま現在に至っています。しかし昨今、都市部を中心とする地価上昇や空き家・空き地問題、さらには外国人による投資的土地取得の増加を背景に、「地価税復活論」が再び浮上しつつあります。制度自体は今も廃止されておらず、“休眠中の税”として政策的な再利用の余地を残しています。果たして、35年前に創設されたこの税制が今後どのような形で再評価されるのか。静かに進行するその議論の背景を探ります。
地価税とは何か
そもそも「地価税」とは何かについて説明します。
地価税は、平成3年(1991年)に「地価税法(平成三年法律第六十九号)」に基づいて創設された国税です。しかし、平成9年(1997年)以降は課税が停止されており、今日に至るまで実際には徴収されていません。なお、「地価税法取扱通達」は平成3年12月18日に制定されています。
現在のところ、租税特別措置法第71条により、「平成十年以後の各年の課税時期において、個人又は法人が有する土地等については、地価税法の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない」とされており、課税は休止状態です。しかし、地価税法そのものが廃止されたわけではなく、法制度としては存続しています。
地価税法第22条によると、地価税の税額は「課税価格から基礎控除額を差し引いた残額に対して税率千分の三(=0.3%)を乗じて計算」されます。
この地価税は、所定の条件を満たす不動産を所有する個人または法人に課される国税です。これに対し、固定資産税はすべての不動産所有者に対して課される地方税であり、起源は明治期の「地租」にさかのぼります。その後、シャウプ勧告を受けて地方税として再構成され、現在に至っています。
地価税の主な課税要件は以下の通りです。
・面積が150平方メートル以上であること
・市街化区域または市街化調整区域に所在していること
・住宅用地以外の用途(例:農地、山林、空き地)であること
ただし、住宅用地であっても、事業用に賃貸している土地や商業用地などは課税対象となります。
地価税創設の背景
地価税は、バブル期に過熱した不動産投機を抑制し、土地の効率的な利用を促進するための施策として導入されました。しかし、バブル崩壊後の地価下落と経済環境の変化に伴い、実効性や負担感が問題視され、1997年以降は課税が停止されています。
地価税の創設から約35年が経過しました。当時の社会状況を知る世代は、すでに50歳代以上になっています。ちなみに筆者は、地価税導入直前、国税庁税務大学校で開催された国際租税セミナーの講師を務めていました。同校では、地価税の運用を担う職員の育成コースも設けられ、不動産鑑定士の資格取得などに向けた研修が行われていました。
地価税「復活」論
それでは、なぜ35年を経てなお、地価税復活が再び議論されているのでしょうか。
第一に、都市部を中心に地価が再び上昇傾向にあることが背景にあります。特に、都心部のマンション等が「資産としての値上がり」を期待して購入され、空室のまま放置されるケースが目立ってきました。いわゆる「ゴーストオーナー」の存在が問題視されており、マンションの管理や意思決定に支障を来す事例も出てきています。
第二に、地価上昇による課税強化や、いわゆる「103万円の壁」に関連する新たな税源確保の一環としての政策的意図があります。2024年12月、国民民主党の古川元久・代表代行が地価税復活の可能性を示唆しました。現時点ではこの意見に追随する動きはありませんが、不動産業界にとっては無視できない話題です。
さらに、2025年の参議院選挙では「外国人の不動産取得」が争点の1つとなりました。都心部の土地や高級マンションを外国人が投資目的で購入し、値上がり益を狙う動きが加速しています。こうした動きに対し、現在休眠中の地価税などを活用して規制や課税強化を図るべきではないかという声も出始めています。
現在、地価税は制度としては存在しながらも「休眠中」の状態です。しかし、地価上昇や空室問題、外国人による不動産投機の増加といった新たな社会課題の出現により、税制の見直し論議が再燃する可能性は十分にあります。地価税が再び「目を覚ます」日は来るのでしょうか。今後の政策議論に注目が集まります。
矢内一好
国際課税研究所首席研究員
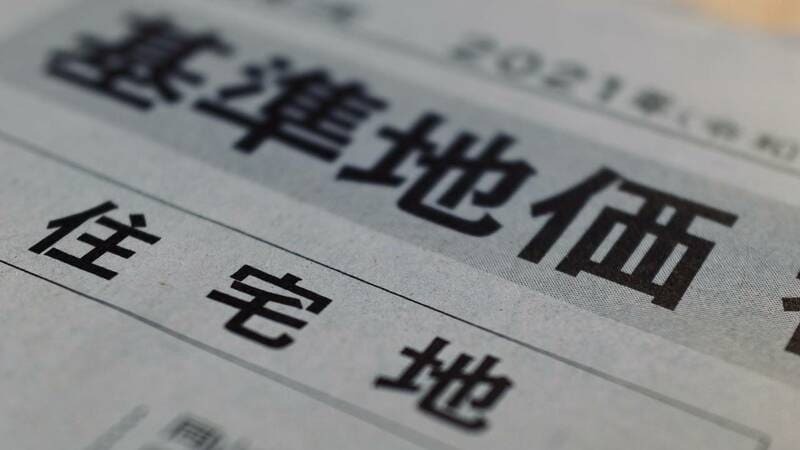


コメント