
経済ニュースでたまに聞かれる、政府による「景気回復宣言」。しかし、サラリーマンや中小企業経営者の実感と、かなりかけ離れたものになりがちです。なぜそのような乖離が起こるのでしょうか。経済評論家の塚崎公義氏が平易に解説します。
景気が上向きのとき、さらに「改善する力」が働くが…
経済学の教科書を開くと、景気が変動する要因として在庫循環等々が記されていますが、こうした要因は過去のもので、現在では重要ではありません(後述)。
景気が自分で方向を変えることは稀です。景気が上向きのときには景気がさらに改善する力が働くからです。企業が生産を増やし、そのために労働者を雇います。雇われた元失業者は給料をもらうので消費をします。物(財およびサービス、以下同様)が一層売れるようになります。企業は増産のために工場を建てるかもしれません。そうなると、鉄やセメントや設備機械が売れるでしょう。銀行も、企業が黒字のときには気前よく設備投資資金を貸してくれるでしょう。サラリーマンも、リストラされる可能性が減ってくれば安心して財布の紐を緩めるでしょう。
反対に、景気が下を向いているときには企業が生産を減らし、労働者を減らすので、失業した元労働者が消費を減らし、景気は一層悪くなっていくのです。
景気の方向を変えるのは「外部要因と財政金融政策」
景気が変動する要因のひとつは、外部要因です。米国の景気が悪化すれば日本からの輸出が減り、日本の景気にも下押しの力が働くのです。リーマン・ショックが記憶に新しいという読者も多いでしょう。急激な円高で輸出が激減し、日本の景気が腰折れした事例も、多数あります。反対に、米国の景気拡大や大幅なドル高円安で輸出が拡大し、日本の景気を回復させた事例も少なくありません。
バブルの崩壊も、景気を悪化させる一因です。バブル期には浮かれた人々が消費や投資を活発化させるので、バブルが崩壊すると反動で消費や投資が激減し、景気が悪化するのです。
バブル崩壊後は、金融危機が発生して景気に厳しい下押し圧力が加わる場合もあります。借金で土地を買った人が破産する事例が増えると、銀行が赤字になります。銀行には「自己資本比率規制」が課せられていて、自己資本の12.5倍までしか貸出を行なうことができないので、赤字で自己資本の減った銀行は貸し出しを制限しなければなりません。「貸し渋り」です。それによって、材料仕入れ代金が借りられなくて倒産する中小企業などが増え、景気が急激に悪化しかねないのです。
外部要因がなくても景気は変動します。政府は財政政策で、日銀は金融政策で景気を調節しようとするからです。景気が悪いときに景気を回復させようとするのは当然ですが、景気がよすぎてインフレが心配なときには、わざと景気を悪化させてインフレを抑え込もうとする場合もあります。財政政策と金融政策については、別の機会に詳述することにします。
景気回復宣言は「水準ではなく、方向」
景気は自分では方向を変えないので、専門家たちは景気の水準よりも方向を重視します。一方で、普通の人は景気の水準を重視するので、ときとしてすれ違いが発生します。
景気が下向きから上向きに方向を変えたとき、政府は「景気回復宣言」を出します。これを聞いた一般人は、違和感を持つのが普通です。「景気は少しもよくない。中小企業の多くは赤字だ」というわけです。それもそのはず、景気の方向が下向きから上向きに変わった翌日は、景気が2番目に悪い日なのですから。
政府が言いたいことは、「今は景気が悪いけれど、方向が上を向いたということは、しばらくすれば景気がよくなり中小企業も黒字になるでしょう。楽しみに待ちましょう」ということなのですから、落ち着いて楽しみに待ちましょう。
景気循環は「高齢化で縮小」
少子高齢化が進んでいます。それによって、消費者に占める高齢者の比率が上がっています。高齢者の所得は年金が主なので、景気の影響を受けません。したがって、高齢者の消費も景気の影響を受けません。加えて、高齢者向けの仕事をしている若者の所得と消費も、景気の影響を受けません。極端な場合、現役世代が全員で介護をしている経済には、景気変動がほとんどありません。そこに向けて少しずつ進んでいるわけです。
景気予想屋である筆者は、仕事が減ることになりますが、引退する年齢なので問題ありません。後輩たちは可哀想ですが。
時代は進化した…「在庫循環・設備投資循環」は過去のものへ
在庫循環というのは、「在庫が増えすぎたので生産を減らす企業が増え、景気が悪化する」といった景気変動のことです。かつて、製造業が経済の中心で、在庫管理技術も稚拙だったころには重要だったのでしょうが、最近では経済のサービス化が進んでいて、製造業の在庫管理技術も進歩しているので、そのような景気変動は稀でしょう。
設備投資循環というのは、好況時に全社一斉に設備投資をすると、10年後に一斉に更新投資が行われるため、10年後に景気がよくなる、という話ですが、最近ではコンピュータ関係のように更新投資のサイクルが短いものも多いので、「全社一斉」ではなく、景気を変動させるほどのインパクトはなさそうです。
今回は、以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。ご了承いただければ幸いです。
筆者への取材、講演、原稿等のご相談は「ゴールドオンライン事務局」までお願いします。「THE GOLD ONLINE」トップページの下にある「お問い合わせ」からご連絡ください。
塚崎 公義 経済評論家
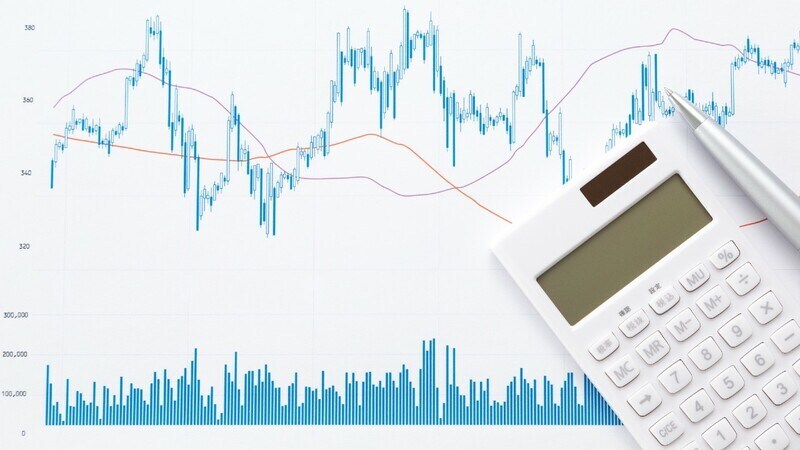


コメント