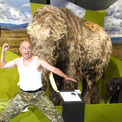

7月12日(土)より10月13日(月・祝)まで東京・国立科学博物館にて開催されている、特別展『氷河期展~人類が見た4万年前の世界~』のプレス内覧会が開幕前日の11日(金)に行われた。本展覧会では、最終氷期の4万年前に、厳しい寒さの中で共に生きていた人類とマンモスなどの巨大な動物たちの姿をドイツのライス・エンゲルホルン博物館とフランスのパリ国立自然史博物館の協力により再現。絶滅動物の再現模型や骨格標本、考古資料、”日本初公開”となるネアンデルタール人とクロマニョン人の実物の頭骨などの展示を通して、絶滅したもの、生き残ったものの命運を分けた氷河期の謎に迫る企画となっている。
内覧会では本展覧会の総合監修を務めた国立科学博物館長の篠田謙一氏が挨拶。「私たちホモ・サピエンスが生まれたのは30万年前のアフリカで、世界に拡散したのは氷河期だった6万年前ですが、そこには別の人類・ネアンデルタール人がいました。1万2000年前、最後の氷河期が終わった時に残ったのは私たちだけ。さらにネアンデルタール人と一緒に滅んだ動物もいました」と解説。本展覧会の趣旨は「気候変動が問題となっている現代に、環境と人間の問題を考えていただくことです」と伝えた。
■アンバサダーのあばれる君も太鼓判!「夏休みの自由研究にもピッタリ」

本展のアンバサダーを務めるタレントのあばれる君は「入り口から終わりまで、捨てるところ一切ナシ!」と太鼓判。ひとつひとつ見て歩くことで「理科の時間50時間くらいの学びがあります!」と見どころだらけの展覧会であるとオススメし「夏休みの自由研究にもピッタリ!」と熱弁していた。あばれる君は、音声ガイドのナビゲーターも担当。イベント後の取材会では音声ガイドを務めた感想や、展覧会にちなんだキーワードの質問に回答した。

――ナレーションを担当した感想は?
膨大な量の原稿を読みました。(量はかなり多かったけれど)読みながら勉強もできるので一石二鳥。ナレーションを録りながら勉強もできる非常に効率のいい時間でした!
――ボケは入っていますか?
――お笑い芸人としてボケが入ってないのは大丈夫?
変な顔をしながら録ったので大丈夫です!
――氷河期にちなみ最近”ヒヤッ”としたことはありますか?
少年野球の塁審をやった時に、まさか自分が…とは思ったのですが、軽い熱中症になりました。普段、ロケも多いので日差しに慣れているつもりだったし、自分がなるわけはないだろうなと。頑丈だと思っていてもなるんです。体はポカポカ暑くて頭もぼーっとするけれど、ヒヤッとする出来事でした。
――もし、氷河期に行くなら、持ってい行きたいものは何?
タンクトップだと危ないので長袖。クロマニョン人に弟子入りして毛皮も手に入れたいです(笑)。クロマニョン人は精神的に豊かな人たち。生きるために槍を作ったり火をおこすのはあたり前だけど、洞窟に絵を描いたり、アクセサリーを作ったりしています。それって生きていくうえでは必要じゃないこと。人を思いやる気持ちや埋葬する悲しみ、そういったものが芽生えてきた人たちだと思うので、ぜひ話を聞いてみたいです。
――人間のルーツが勉強できる展覧会です。あばれる君自身のルーツは?
雄大な自然のある福島県です。東北も冬はかなり寒いですが、雪深い地域で育ったので寒さは非常に大好き。氷河期とも通じるものがあります。寒いところって口数が減るけれど、我慢強くもなります。寒さに絶え抜く、厳しい寒さが僕のルーツです。
――寒さがルーツならスベった寒い空気も大丈夫?
自分はそうは思いません!!(と即答&絶叫)キレイに締まりましたね(とご満悦)。

■展示は3章構成。日本初公開の頭骨はあばれる君もイチオシ
展示は「第1章:氷河期ヨーロッパの動物」「第2章:ネアンデルタール人とクロマニョン人」「第3章:氷河期の日本列島」の3章構成で展示。展覧会入口には「会場マップ」も設置されているので、参考にしよう。会場内は撮影OK(一部、撮影できないものもアリなので要チェック!)なので、あばれる君が「自由研究にもピッタリ!」とオススメしたように、写真に撮って参考資料として持ち帰ることができるのもうれしい。
「第1章:氷河期ヨーロッパの動物」で展示されているのは過酷な環境を生きていた「氷河期のメガファウナ(巨大動物群)」。ケナガマンモス、ギガンテウスオオツノジカ、ステップバイソン、ケサイ、ホラアナライオン、サイガ、ホラアナグマなどの骨格標本や生体復元模型で氷期に生きた動物たちを紹介し、巨大生物の謎に迫るコーナーとなっている。ライオンやクマといったなじみのある動物も並んでいるが、現生のものよりもより迫力や凄みを感じるような雰囲気を漂わせているのが印象的だった。
「第2章:ネアンデルタール人とクロマニョン人」では日本初公開となる世界一有名な人骨、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスであるクロマニョン人の実物の頭骨や、彼らが使っていた道具や装飾品などを展示。私たち人間の祖先となったクロマニョン人に対し、ネアンデルタール人は4万年前までに姿を消している。その違いは何だったのか。両者はどのような文化を築き、何が生き抜くための知恵であったのを比較しながら解説。両者の命運を分けたものは一体何なのか。体格の違いや、狩猟方法・狩猟対象の違い、さらには道具の違いなどを見比べることができる、興味深いコーナーとなっている。ちなみにあばれる君のイチオシ展示はこのネアンデルタール人とクロマニョン人の頭骨とのことだった。
「第2章:ネアンデルタール人とクロマニョン人」と「第3章:氷河期の日本列島」の間には「氷河期解説」&体験コーナーも。テキストや映像での解説に加え、動物の毛や歯に触れる展示も。動物の名前は伏せてあり、モフモフ毛やちょっと硬めの毛を触りながら、どんな動物の毛なのかを予想するクイズ形式で楽しめる展示となっている。歯についてはどの動物のものなのかは最初から明かされているが、形や硬さをじっくりと堪能しながら、どんなものを食べていたのかなどを想像するのも楽しい。

「第3章:氷河期の日本列島」では日本三大絶滅動物であるナウマンゾウ、ヤベオオツノジカ、ハナイズミモリウシと人骨、石器類から当時の日本列島で人類と動物がどのように暮らしていたのかを詳しく紹介。氷河期の海面低下により現在とは大きく異なる姿をしていた日本。当時から日本列島は南北に長く、寒冷な地域から温暖な地域まで、多様な環境が広がっていたことから現代との繋がりを感じつつも、海面は現在よりも60から120メートルほど低く、北海道が樺太や大陸とも繋がっていたこと、本州と四国、九州も繋がった島であったことに驚くと同時に、人類が日本にたどり着いた氷河期からの時の流れ、環境の変化などを痛感する。
第2会場では「氷期・間氷期サイクルと植生」が学べる展示と「特別展特設ショップ」を設置。展覧会オリジナルグッズだけでなく、書籍や模型などの学べるアイテムから、フジサキタクマ、ヨッシースタンプ(R)、オカタオカ、MORN CREATIONS & Steve Chanなど国内外の有名クリエイターとのコラボグッズなども盛りだくさんだ。
夏の厳しい暑さにうんざりしてしまう毎日だが、厳しい寒さを耐え、生き抜いた人類と動物たちの4万年前の世界を人類の目線で楽しんでみてはいかがだろうか。













コメント