
「“孤独”に寄り添うはずの支援員が“孤独”を抱えていました」 ―― 困難を抱える人々に対して、伴走支援を続けてきたNPO法人抱樸(ほうぼく)。kintone導入以前は、情報共有とコミュニケーションを担う基盤がなく、他部門の動きが不透明な中で被支援者と向き合っていたという。
サイボウズは、kintoneユーザーの事例イベントである「kintone hive 2025 fukuoka」を開催。3番手で登壇したNPO法人抱樸の蔦谷聡氏は、“誰も見捨てない”という同法人の理念が反映されたkintone活用について披露した。
“孤独”に寄り添うはずの支援者が“孤独”に直面
NPO法人抱樸は、「誰もが見捨てられない社会」の実現を目指し、30年以上前にホームレス支援から活動を開始した。今では、子どもや高齢者、障害を持つ人、刑務所出所者など、様々な困難を抱える人々に対して、全29事業を通じた伴走型支援を展開している。
例えば、蔦谷氏が勤務する「地域生活定着支援センター」は、生活に不安がある刑務所出所者を、地域の福祉サービスにつなげる機関である。対象者には、親からの虐待、学歴や就労歴の不足、潜在的な障害など、様々な困難が複雑に絡み合い、犯罪に至ってしまった人々が含まれる。そして彼らを、単一の部署だけで支えることは難しいのが現状だ。
そのため抱樸では、地域を超え、多くの部署が専門性を活かしながら、対象者と密接に関わる支援体制を構築してきた。この体制においてもっとも重要なのが、“部署間の情報共有とコミュニケーション”だという。
しかし、kintone導入以前の情報共有ツールは、電話とFAX、そして全職員が所属するメーリングリストのみ。個人情報といった機密性の高い内容は、メーリングリストでは共有できず、他部署や法人全体の動きも不透明。この連携のしにくさが、対象者の不利益につながる危険性をはらんでいた。
「さらに、一人ひとりは必死で支援しているのに、『一人きりで対象者と関わっているんじゃないか』という気持ちに陥ってしまう。まさに“孤独”に寄り添うはずの支援員が“孤独”を抱えてしまう状況にありました」(蔦谷氏)
“誰も見捨てない”理念をkintone推進にも応用
抱樸は、こうした課題を解決すべく2020年にkintoneを採用。「コミュニケーション促進」「チームとコンサルの活用」「伴走支援」という3つの軸で導入を進めている。
第一の軸は「コミュニケーションの促進」だ。手軽に情報発信できるkintoneの「ピープル」機能を活用。何気ない日常の出来事を投稿するなど、職員同士の個人的なコミュニケーションを推奨した。アカウントを持つ職員だけが閲覧できる「鍵のかかった社内SNS」としてkintoneを運用することで、“個性や顔が見える関係性”を育み、対象者支援の土台にしている。
第二の軸は「チームとコンサルの活用」だ。kintoneを担当するチームは、デイサービスや総務など、部署横断的なメンバーで構成されている。「パソコンに詳しい」という理由で相談を受けることが多かった職員で結成され、蔦谷氏もその一人だ。チーム化、すなわちプロジェクト化することで、個々の職員が抱えていたIT関連の対応が、法人全体に貢献するIT施策に昇華。そしてkintoneは、孤独に対応する職員をつなぐ基盤となった。
さらに、プロジェクトの体制を強固にすべく、ITコンサルタントのAISICにサポートを依頼。対象者データベースのkintone移行において、伴走支援を受けた。このコンサルタント活用で、kintoneの拡張性や限界、最適なデータ蓄積の方法、そして伴走開発のエッセンスを学び、職員に展開していく。
第三の軸は「伴走支援」。これは抱樸が最も大切にしてきた理念でもある。どんなに便利なkintoneアプリを作っても、変化に対する抵抗感が生じる。抱樸では、その抵抗感を否定せずに、ひとつの価値観として尊重。「見つける。見捨てない」「相手の価値観を尊重する」「向かい合うのではなく同じ方向を向く」という伴走支援で心掛けていることを、kintoneの促進にも応用した。
職員からの質問を受け付ける「Q&Aアプリ」を作成し、寄せられた質問には必ず対応し、さらに、困っていることがないか“おせっかい”することでつながりを保った。他にも、イラストを活用して目的のページにたどり着きやすくするなど、利用者と同じ目線に立った改善も重ねている。
それでも根強い抵抗があったのが、紙からの脱却だ。そこで、kintoneの情報を帳票形式で出力できるプラグイン「k-Report」を採用。入り口はkintoneでも出口は慣れ親しんだ紙という形で、kintoneに触れてもらうことを優先した。短期的な結果ではなく、つながり続ける時間に価値を置くという、抱樸らしいアプローチが貫かれている。
職員に寄り添うための「居場所」を担うkintone
これらの取り組みの結果、kintoneは単なる業務システムではなく、職員が集える場所になっている。全職員に個人アカウントを付与して、所属(部署・プロジェクト)ごとにスペースを作成、秘匿性のあるスペースにはアクセス制限をかける。kintoneで、離れた場所にいても一体感を感じられる“疑似オフィス”を築いた。
対象者データベースもほぼ全部署でkintoneに移行され、グラフや集計機能によって業務も効率化された。そして、抱樸で作られたkintoneアプリの総数は461個に上り、その多くは、現場職員が課題解決のために作成したものが占める。伴走支援によって、職員一人ひとりが開発フローを学び、実践する文化が根付いた結果が現れているという。
その他にも、抱樸らしいkintone活用として「対象者専用スレッド」がある。特に緊急性の高い対象者を、複数の職員で支援するための情報共有の場であり、通知機能によってリアルタイムで密な連携を可能にする。「kintoneの仕組みと抱樸の理念が、現場ニーズによって結びついている」と蔦谷氏。
また、理念を基盤に活動する抱樸にとって、対象者や関わる人々と紡いでいく“ストーリー”は最も重要な資産である。kintoneは、そのストーリーを未来へ残していくための器としても欠かせなくなっている。
蔦谷氏は、「支援をする側でも、孤独になる瞬間はやってきます。それでも、職員が対象者の孤独に寄り添えるのは、抱樸という居場所があるからです」と語る。そして、「開発チームが職員の孤独に寄り添えるのは、kintoneという居場所があるからです。kintoneで抱樸に関わる全ての人を孤独にしない。これが私たち抱樸kintoneチームの想いです」と締めくくった。
プレゼン後には、サイボウズの岡地麻起氏により質問が投げられた。
岡地氏:鍵のかかったSNSという表現がありましたが、とても面白い発想だと思いました。kintoneは、コミュニケーションの基盤としても浸透しているのでしょうか。
蔦谷氏:実際に、何気ないコミュニケーションまで、kintone上で交わしているのを見かけます。そういったやりとりを見ると嬉しくなりますね。
岡地氏:今回、パートナー企業のAISICさんの伴走支援を受けられましたが、依頼して良かったところを教えてください。
蔦谷氏:kintoneのことを何も分からない中、作りたいイメージを相談すると、機能やプラグインなど様々な可能性を提示してくれました。その中から私たちに合うものを一緒に探してくれたことが、一番ありがたかったです。
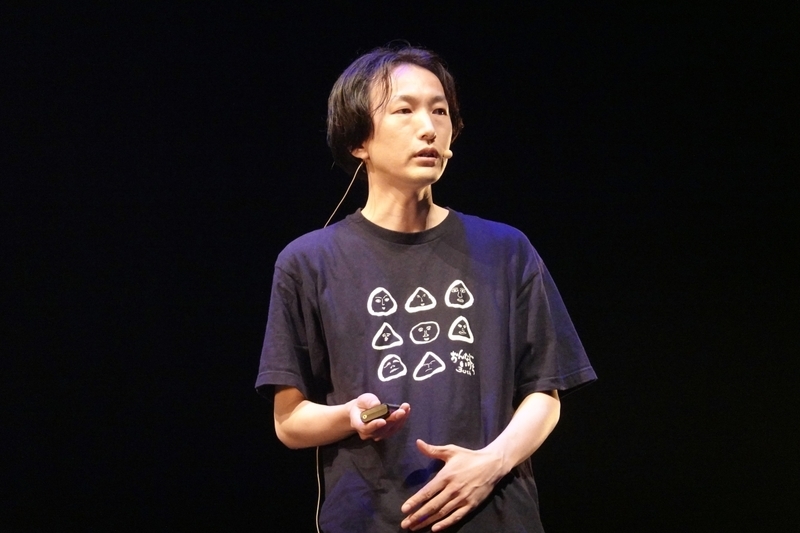


コメント