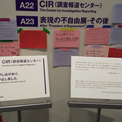
会場ロケーションの妙に地元民も感激
今回のトリエンナーレで印象に残ったことの一つに、ロケーションの妙というのがあった。これまでにも、主会場となる愛知芸術文化センターや名古屋市美術館のほか、同じ名古屋市内の繊維問屋街である長者町や、あるいは県東部(三河地方)の岡崎市や豊橋市などが会場となり、展覧会などが行なわれてきた。ただ、私が観たかぎりでは、主会場以外の会場は、盛り場からやや離れていることもあってか、その地域の活性化にはいまひとつ結びついていないような気がした。少なくとも芸術“祭”と呼ぶにはちょっと寂しい雰囲気だった。
しかし今回、新たに会場となった名古屋市内の四間道・円頓寺(しけみち・えんどうじ)エリアと豊田市美術館・豊田市駅周辺エリアは、地域活性化という意味でどんぴしゃの選択だったと思う。
豊田市の会場では、これまでにも現代アートの展覧会を積極的に開催してきた豊田市美術館を中心に(いままでトリエンナーレの会場に選ばれなかったのが不思議なくらいだ)、前編で紹介したホー・ツーニェンによるインスタレーションが設けられた旧旅館・喜楽亭をはじめいくつかの場所で作品の展示が行なわれた。ラグビーワールドカップ開催と重なったこともあってか、街も活気に満ちていた。
個人的には、四間道・円頓寺が会場となったのはうれしかった。円頓寺商店街は、愛知県図書館からの帰りがけ、名古屋駅への抜け道としてよく通るのだが、10年ほど前は絵に描いたようなシャッター通り商店街だった。それが近年、おしゃれな飲食店があいついでオープンし、またボルダリング場や芝居小屋など新たなスポットもできたりと、しだいに活気づき始めた(同商店街の再興については、山口あゆみ『名古屋円頓寺商店街の奇跡』という本にくわしい)。商店街のすぐ近く、堀川沿いの四間道と呼ばれる通りには江戸時代から続く商家が軒を連ね、一部は料理店などにリノベーションされて再利用されている。
今回のトリエンナーレでは、この地域にある店舗などの建物を展示場にあてるとともに、商店街の名前の由来となった「長久山円頓寺」の駐車場の特設ステージでは、毎週木曜〜日曜の夜に日替わりでアーティストを招いてデイリーライブも開催された。鷲尾友公が描き下ろした壁画(トリエンナーレの出展作品)が背面を飾ったステージには、曽我部恵一、呂布カルマ、ぱいぱいでか美、眉村ちあき、原田珠々華、後藤まりこ、堀込泰行、七尾旅人などじつにバラエティに富んだアーティストたちが出演した。ライブは無料で、近くの飲食店のオープンスペースで食事したり酒を飲んだりしながら観ることもできた。
円頓寺は、東京からトリエンナーレを目的に愛知を訪れた知人たちにも好評だった。美術展を見てまわるとともに、飲んだり食べたりもできる。トリエンナーレが地域の活性化と結びつく様子がはっきりと見られたのが、このエリアだった。地元民としては、今後もよそから来た友人知人に自信をもって連れていけるという確信が得られた。
作品のあいだに浮かび上がる関係性
同じモチーフやテーマをとりあげながらも、作家によって趣向の異なる作品が観られるのも、国際芸術祭の醍醐味だろう。今回のトリエンナーレでは、台湾をモチーフにした作品がいくつか観られた。たとえば、毒山凡太朗の「君之世」という映像作品(四間道・円頓寺エリアで展示)は、台湾の老人たちに戦前の日本統治下の記憶についてインタビューしたもので、そこでは日本語の歌で覚えているものはあるかと訊かれた老人たちが、「蛍の光」や「仰げば尊し」、「君が代」、さらには「同期の桜」や「月月火水木金金」といった軍歌・戦時下用を懐かしそうに歌う様子も収められていた。
これに対し、名古屋市美術館で展示された藤井光の作品「無情」は、日本統治下の台湾で製作された国策プロパガンダ映画「国民道場」と、藤井の手になるカラー・高解像度の映像をあわせて上映したものだ。前者は、台湾の人たちを「日本人化」するために設けられた国民道場の様子を記録したもので、後者ではその道場に集められた人々の動き(行進や儀礼など)が現代の若者たち(愛知県内で学び働く外国人などだという)によって再演されている。現代の若者たちが一糸乱れず体を動かすさまは、どこかグロテスクにも感じられた。
同じ日本統治下の台湾をモチーフにしながら、毒山作品がノスタルジックな印象を与えるのに対し、藤井作品からは、現地の人たちを日本人と同化させようとしたかつての大日本帝国の国策に対し批判的な姿勢がうかがえる。二つの作品をあわせて観ると、物事は切り口しだいでさまざまな見方ができるということをあらためて実感する。
豊田市の会場では、過去に国家によって設置されたモニュメントをモチーフとした作品が2点観られた。一つは、キューバのレニエール・レイバ・ノボによるインスタレーション「革命は抽象である」で、作品を構成する一要素として、ロシア国内に現存するガガーリン像(旧ソ連が生んだ人類初の宇宙飛行士の銅像)の実物大のレプリカ(部分)が展示された。もう一つは、愛知環状鉄道の新豊田駅前の広場に置かれた「↓(1923-1951)」という小田原のどかの作品である。こちらは、戦前に東京・三宅坂にあった寺内正毅元帥騎馬像の台座(5メートル近くある)を再現したものである。展示に際しては、像に代わって見学者が台座の上に立つことができた。会期終了後に作家が明かしたところによれば、この台座は、皇居のある方角に向けて設置されていたという。
両作品のモチーフとなったモニュメントは、背景となる思想こそ違うが、英雄をかたどった銅像であること、また、人々に威圧感を与えるようなスケールなど共通点も少なくない。
このようにトリエンナーレ全体を通して観ていくうち、対照的だったり、あるいは類似的だったりと、作品どうしのあいだで関連性が浮かび上がるのが面白かった。インスタレーションが複数の要素からなる作品であるのと同様に、複数の作品で構成されるトリエンナーレのような芸術祭もまた一つの作品ということもできるのではないか。
そこで気になるのは、今回のトリエンナーレで、一度は中止に追い込まれながらも閉幕まぎわに再公開された「表現の不自由展・その後」は、トリエンナーレ全体のなかではどのように位置づけられたのだろうか、ということだ。そう考えるにつけ、今回、観る機会が得られなかったのがつくづく惜しまれる。
「表現の不自由展」をもってトリエンナーレ全体を語りがち問題
今回のあいちトリエンナーレをめぐる一連の報道を見ていて気になったのは、どうも「表現の不自由展・その後」という一企画にすぎない展覧会をもってトリエンナーレ全体を語る向きが目立ったことである。
これにかぎらず、個別の事例をとらえて、全体まで判断してしまう傾向は現在、あらゆるところで見られる。たとえば「週刊文春」という雑誌は、「文春砲」の語に象徴されるセンセーショナルなスクープ記事のイメージでとらえられがちだが、本誌に目を通せば、それは同誌のほんの一要素にすぎず、そこには和田誠の表紙にはじまり小説やコラムなどさまざまな要素でなりたっていることはすぐにわかる。だが、雑誌や新聞があまり読まれなくなり、ポータルサイトでニュースを知ることが多くなったいま、そのことは忘れられがちだ。昨年の雑誌「新潮45」に掲載された某議員の記事が非難され、結果的に雑誌そのものが廃刊されるにいたった一件も、そうした傾向から生じたといえるのではないか。
そんな時代だからこそ、あいちトリエンナーレ2019の主催者は、「表現の不自由展・その後」の開催にあたってもう少し慎重になるべきではなかったか(なんてことは、いまさら私が指摘するまでもないだろうが)。「少女像」や「天皇の肖像」といった言葉を一人歩きさせれば、どんな事態が起きるのか、ある程度は予想できたはずである。事前に、作品の文脈について、丁寧に説明する必要はあったのではないか。今回、あの展覧会に肯定的な態度を示した人のなかにも、作品について十分に理解しているとはいいがたい発言をSNSなどで見かけただけに、よけいにそう思う。
もちろん、いったんは中止されながらも、最後の最後で再公開にこぎつけたことは、私も素直に歓迎したし、意義あることだったと思う。鑑賞者の人数を絞っての公開形式になったのも、警備などを考えれば、仕方なかったことは理解できる。ただ、トリエンナーレのほかの展示から、あの展覧会だけちょっと浮いてしまったという感は否めない。観られなかった者の負け惜しみなのかもしれないが、今回のトリエンナーレではそれだけが残念であった。
願わくば、今回の一件でけっして萎縮することなく、あいちトリエンナーレには今後も果敢な挑戦を続けてほしい。一介のアート愛好者として、また愛知県民としてもそう思う。(近藤正高)



コメント